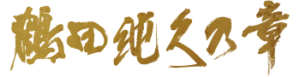ぐい呑

ぐい呑の造り方
ぐい呑みの場合お茶碗と違い生地となる土を焼き〆たほうが使い勝手が良くなると思います。茶碗はお点前の時に水に通して準備したり、お湯に通して点てたりして生地に水分を含ませますので焼き締まりが足らずとも良いのですが、ぐい呑みはそこまで気を遣うのは一般的では無いので出来れば焼しめた方が良いと思います。
GUINOMI
ぐい呑の作り方の前にぐい呑とは何かを考えたいと思います。
1600年以前で古唐津の窯の物原から出る全体の陶片の数量から考えるとぐい呑の陶片が出る割合は全体の5パーセントにも満たないぐらいの量しか出てきません。これは古窯群にもよるのですが、抹茶を呑む茶碗と同等ぐらいだと思います。
今日ぐい呑は主に酒器と考えられていますが、当時のお酒も飲まれていたと思いますがその生産量の少ない希少価値からいうとべつの物を呑むために作られていたように思われます。当時の焼き物を使うとなると富裕層の人たちが使い、庶民にはなかなか手の届かない物でしたでしょう。その富裕層で流行っていたのが当時の健康補助食品「茶」であったと考えられます。粉茶を飲むのに使っていたのが「茶碗」、葉茶を飲むのに使っていたのが「ぐい呑」だと思います。「ぐい呑」という名前は後の人が付けたのでしょうから当時はなんと言っていたのか解りませんが、「茶碗」は文字通り「茶を飲む碗」でしょうから「ぐい呑」は「小茶碗」とでも言っていたのでしょう。今日の「煎茶碗」はこの同類と思われます。
※ここで押さえておきたいのは「古窯からの出土の茶碗は沢山出てきているのでは」とお考えでしょうが「碗」は沢山出てきていますが「茶碗」の目的で作られたのはごく少量です。見立ての茶碗と茶碗に作られたのは別とお考え下さい。
江戸時代に入り世の中が安定してくるとお酒を飲む「盃」が大量に作られるようになります。今日ではこれら全体を含めて「古唐津のぐい呑」と賞賛されていますが、ぐい呑を造る側から言いますとそこは分けて考えた方が良いと思います。
ぐい呑の造り方においては全く茶碗の造り方と同様で、重要な要素が三つ有りますので別ページ「茶碗の造り方」を参考にして頂きご覧下さい。
ぐい呑みの場合お茶碗と違い生地となる土を焼き〆たほうが使い勝手が良くなると思います。茶碗はお点前の時に水に通して準備したり、お湯に通して点てたりして生地に水分を含ませますので焼き締まりが足らずとも良いのですが、ぐい呑みはそこまで気を遣うのは一般的では無いので出来れば焼しめた方が良いと思います。
こだわりのある器
ぐい呑みとは誰でも作れる器ですが、買い求める側からすると作家さんが作る全体の作品の中でその位置づけは上位の所に来ると思います。その作家さんの代表的な作品を欲しいとき、大きな作品でなくお茶道具でなかったらその次に来るのはぐい呑では無いでしょうか。
造る側の作家の方も、ぐい呑と言う器の位置付けは位置が高く茶碗は造れずとも自分の代表的な作風を入れこだわりのある器として造ります。ましてや他の器より大きさが小さく存在感も少なくなりがちですので、より以上に変化を持たせ存在感が大きい器にしなくてはなりません。
「茶碗の造り方」ページでも書いたように最も重要なことはストーリー性(話題)が有るように造らなければなりません。昔より約束事として伝えられてきた技術や技法・装飾法など器にまつわるお話のように作家が知識と鍛錬で積み重ねてきた要素を器に込め、それを求めたお客が知人にお披露目します。お披露目でその器について話が進み時間を忘れるぐらいのストーリー性があれば最高の器となるでしょう。
至福の一杯をぐい呑で
人にはそれぞれ違った「至福の一杯」があると思います。紅茶・珈琲・抹茶・煎茶・日本茶・中国茶などの喫茶系や、日本酒・焼酎・ウィスキー・ブランディ・ビール・カクテルなどの飲酒系、または様々な健康補助食品などなど。その一服を味会うために費やす手間と暇と経費は人生の内でも結構な部分を占めていると思います。
またそれも人とのコミュニケーションを図るのにも大事な要素と言って過言では無いでしょう。まさに茶道のお茶席の世界がその様に、「一期一会」と言いますが、人との出会い、器との出会い、「至福の一杯」を味会うためにいろんな物語が生まれます。
皆様がぐい呑を求めるとき、作家さんのぐい呑を拝見するときなど上記の説明が役に立てばと願っています。
ただ、例外はあると認識をお願いします。あくまでも参考にして下さい。