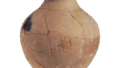歴史上、古代という時代は統一国家の成立を基盤として、欧亜大陸にそれぞれ特色のある文明がいっせいに咲き誇った時代です。
やきものの世界では、原始時代以来の長い伝統をもった酸化焰によある赤い素焼の土器のほかに還元焰による灰色の硬陶が生まれ、やがして灰釉を施した高火度焼成の施釉陶器が出現しました。その一方、鉛釉に種々の呈色剤を加えた低火度焼成の彩釉陶器が生まれるなど、多彩なやきものが相ついで登場したのでした。このように酸化焰と還元焰、無釉の焼締陶と施釉陶という、今日のやきものの基礎はすべて古代のうちに形づくられたのです。したがって、古代は単一なものから多様化への展開を遂げた時代であったともいえましょう。
わが国の古代は通常、大和朝廷の成立を基盤とした古墳時代の始まりから、平安時代の終りごろ、藤原氏による貴族政権が亡びて源平の武士階級による封建国家の成立までの、すなわち3世紀末から11世紀末までの約八百五十年あまりを指しています。この長い年月の間に登場したわが古代のやきものには、土師器、黒色土器、須恵器、三彩・緑釉陶器、灰釉陶器など、さまざまのものがあります。これらのやきものは古代に入っていっせいに出現したものではなく、古代国家の発展に即して相起こしたものであり、その原型は中国・朝鮮など古代アジアの先進諸国家のそれに負っています。
それでは如上のわが古代の土器 陶器はいつごろ、どのようにして出現し、また当時どのように呼ばれていたものでしょうか。さらにまた、いつごろどうして消え去ったものであるか、出現の順序に即してそれぞれのやきものがもつ性格について初めに述べましょう。
現在われわれが土師器と呼んでいる赤い素焼の土器は、周知のように弥生式土器の後身であり、古墳時代以後のものを指しています。
『延喜式』 主計上に「贄土師 坏作土師 玉手土師」 などがあり、『倭名類聚抄」には「釈名云 土黄而細密日日埴 常識反(和名波爾)」とあるところから付けられた名称ですが、「土師器」の名称を用いた最も古い例は「職員令集解』の「検校土師器」 や 「営繕令集解』の「瓦器 謂陶器也 土師器亦同耳」などであり、それ以前は「土「器」 「埴器」であり、呼称は「ハニノウツワ」でした。土師器が弥生式土器とおなじ酸化焼成の素焼の土器であり、ひと続きのものであるとするならば、弥生式土器から土師器への転化はいつごろ、どのようにして行なわれたのでしょうか。最近の考古学の成果によると、かつて両者の区別の指標とされた小型丸底土器の前段階に、複合口縁をもった壺や甕・鉢 高杯を主体とした瀬戸内の 「酒津式」あるいは山陰の 「九重式」など、最も古い土師器の存在が西日本において指摘されており、その畿内への影響によって、古墳時代初期の土師器が生成したという考え方が支配的になっています。これに対して内における土師器の発生は弥生式土器からの自生と捉え、古墳の発生を契機として弥生式土器と区別し、その最も古い型式を「庄内式」 として捉えています。いずれにせよ地域色のつよい初期の土師器から小形丸底土器が畿内において定型化し、その全国への波及によって、統一的な土師器の完成が考えられるのです。つぎに土師器の終末をいつに求めるかは、その内容をどう捉えるかによって、いろいろな考え方が生まれます。現在の一般的な考えは、土師器を日常的な食器の面から捉え、東海地方で生み出された灰釉陶器が一般に普及する10~11世紀にその終末を求めようとしています。しかし、こうした現象は東日本において広汎にみられますが、西日本においては土師器から黒色土器へ、さらに瓦器へ、それぞれの転化に応じて土師器が段階的に減少しており、完全に消滅にいたるのははるか後代のことです。東日本における灰釉陶器の普及あるいは西日本における瓦器の成立の時点を求めれば、11世紀は一つの転期とすることも可能でしょう。しかし、各種の陶器が出現した段階においては、なおかつ土師器が他種のやきものに代ることのできないその特性は、むしろ煮沸形態にあります。したがって、煮沸用器として土師器の場・釜などが鉄製のそれに代る時点にこそ、むしろ土師器の役割の消滅を考えるべきでしょう。鉄製煮沸用具の普及は鎌倉時代に入ってからの現象です。
土師器と並んで古代には黒色土器と呼ばれる軟質の土器があります。これは土師器の内面あるいは内外両面を磨き、器面に炭素粒を吸着させて漆黒色とした土器であり、8世紀後半以降、西日本において盛行しました。しかし、中部山岳以東の東国では6世紀以降、須恵器の器形を写した杯などにこの手法が用いられており、内黒土師器と呼ばれています。
つぎに古代において土師器とともに最も主要なやきものであった須恵器について述べましょう。土師器が酸化焰による赤い素焼のやきものであるのに対して、須恵器は轆轤成形と還元焰焼成による灰色の硬質のやきものです。『延喜式』には「陶器」という文字が当てられており、『和名抄」 には 「瓦器一云陶器 陶訓須恵毛能」と記されていて、当時「スエモノ」と呼ばれたことが知られます。須恵器という言葉は施釉された現代の陶器と区別するために、昭和に入って用いられるようになった学術用語です。かつて祝部式土器、陶質土器と呼ばれたこともあります。
須恵器の源流を求めますと、南鮮の伽耶・百済の陶質土器、新羅焼から中国の殷代にすでに行なわれていた灰陶にまで遡り、広く東アジア諸地域に拡がっていた灰陶系のやきものの一支脈として生成したものです。すなわち、南鮮の三国時代の陶質土器との著しい類似性や、中国南部において発達した窯法の系統に属するところから、中国南部に発し、南鮮を経て、しだいにその製法が伝わったものと考えられます。それでは須恵器の生産の開始をいつごろに求め得るでしょうか。しばしば引用されるように、『日本書紀』 雄略七年(463)の条に記された「新漢陶部高貴」 が百済から貢上された今来才伎 (イマキノテヒト) であったと考えられることから、須恵器の発現をそのころに求めようとする考え方が古くから支配的でした。しかし須恵器の発生をより古く求める考え方が一方であり、大和朝廷の南鮮進出を契機として、4世紀後半代にその製法が伝播したとする説もある (森浩一説)。すでに古く、南鮮における灰陶系の陶質土器である金海式土器が、対馬 壱岐のみならず、大阪湾沿岸の後期弥生式土器に伴って用いられており、北九州の弥生式土器における敵打法の採用、土師器の丸底への変化など、漢式土器の影響が現われていたことを考えれば、その発生を古く求めようとする考え方も出ないではありません。しかし、須恵器の製作技術はすぐれた轆轤技術と良質の陶土、還元焼成のための大量の燃料の確保という、弥生式土器や土師器のような小規模な共同体生産の限界をこえた、より広域的な生産体制を必要とします。したがって、このような体制の成立を可能ならしめた5世紀前半代にその開始を求めるべきであろうという考え方が支配的になってきています。
それでは須恵器はいつごろまで用いられたものでしょうか。須恵器生産が開始され、古墳時代におけるその全国的な中心であった大阪府の陶邑窯は5世紀から10世紀にかけて、五百基以上の窯の存在が知られています。その築窯の変遷を数量的にみますと、5~6世紀に三百基以上であったのが、7世紀には八十基、8世紀以後の二百数十年間にわずか百十基しか築窯されていないことが知られています。
そして10世紀代のうちにほぼ生産が終息したと考えられています。このような陶邑窯の生産の衰退は、古墳時代以来の過剰生産の結果もたらされた山林の荒廃によるものであって、「三代実録』 の貞観元年の条に記された河内・和泉両国の燃料争い (陶山争論)がその動向を示しています。もちろん、資源問題のみならず、律令制の衰退に基づく生産体制の変貌も大きな原因の一つです。このような傾向は西日本の須恵器生産にも共通した現象でした。しかし東日本ではむしろ古墳時代の終りごろから生産が上昇し始め、平安時代に入って隆盛を迎えるのであって、11世紀末ごろ、中世窯に転換するまで生産が継続するのです。
土師器 黑色土器
周知のように、土師器は弥生式土器の後身であり、原始時代以来の酸化焰焼成による、赤褐色ないしは黄褐色をした素焼の土器です。弥生式土器から土師器への転換は、さきに述べたように、外来の要因に基づくものではなく、古墳時代の開始という政治的要因による内在的なものでした。したがってその移行は移的であり、特徴的な祭祀土器を除けば、当初の器形や製作技術に基本的な相違はありません。
土師器の器形は基本的には、貯蔵用の壺、煮沸用の甕、食器としての杯・・ 高杯、調理具としての鉢類のほか、祭祀土器としての壺器台があります。ごく初期には弥生式土器の名残りとして手焙形土器などの特殊なものがあります。5世紀中ごろ、須恵器製作技術の導入にともなって、新たに煮沸土器として韓竃が、また角付盤など若干の器種が追加されるとともに、須恵器をつくり得なかった東国の地域では、須恵器の器形を真似た杯・などがつくられています。
それらの杯のうちには内面に炭素を吸着させた内黒土師器もあります。
土師器の器形は、7世紀後半以降に大きな変化をもたらし、杯に代わって新たに碗盤皿などの食器類が豊富になっていますが、須恵器の器形の変化と対応しており、そこに大きな生活上の変化があったことを示しています。このように土師器の器形はきわめて豊富であり、一般には須恵器の出現によって衰退したかのごとく考えられがちですが、むしろ競合して発展しており、とくに煮沸形態は鉄製の鍋釜が普及する鎌倉時代まで、基本的な生活用具として用いられたのでした。
つぎに土師器の製作技術についてみますと、まず弥生式土器にくらべて精良な土が用いられていることが指摘できます。弥生式土器はまだ地域によって精粗の差が大きかったですが、土師器は比較的よく似た土に統一されています。成形には手づくね、巻き上げ、輪積の三方法があり、杯・皿・碗など小形品は手づくねによって、壺・甕などは後二者の方法が用いられました。轆轤の使用は8世紀末以降のことです。甕類は条線の刻みのある器具で叩き締めて成形されています。整形は削りによって器厚を整えたのち、布でなでたり、刷毛・櫛・によって細部の調整を行ないました。土師器の焼成は弥生式土器の延長上に考えられており、大阪府喜志遺跡のような方形の土壌で、700~800度位の温度で焼かれたとみられますが、古墳時代の窯はよく判っていません。奈良時代になりますと、三重県水池遺跡で多数の三角窯が発見されており、平安時代には石川県小松市の戸津古窯跡群にお丘陵斜面を削った馬蹄形の窯が知られています。いずれも上部構造については明確ではありません。弥生式土器が飾られた土器を豊富にもっていたのに対して、土師器は無文を原則としています。ごく初期には直弧文風の刻文ある土器も知られていますし、特殊な祭祀土器に刻線竹管文を施すものがわずかばかり知られているだけです。しかし器面を丹彩で飾ったいわゆる丹塗土師器は、東国においてかなり後までつくられています。
土師器が主要な日常用具として用いられた時代は4世紀から11世紀ごろまでの約七百年である。素焼の土器を土師器の後裔と考えるならば、ゆきひら、ほうろくのように今日までその残存形態をみることができますが、基本的には鉄製煮沸用具との交替によってその生命を終わったとみるべきでしょう。土師器はさきに述べたように、七百年の長い歴史をもっていますが、大きく分ければ須恵器出現以前、須恵器導入から7世紀後半まで、7世紀後半から11世紀までの三段階の変遷を遂げているいま、その変遷の過程を三段階に分けますと、まず第一段階(4世紀~5世紀後半) は須恵器出現以前の約二百年間で、関東の「五領」 「和「泉」 両期、畿内の「庄内」 「布留」 両期を含んでいます。この段階は古墳時代の開始という政治的変革を契機として、各地域において弥生式土器から土師器への転換が始まる時期であり、やがて小形丸底器と器台の組み合わせに象徴されるように、畿内的な土師器によって全国に画一性の進行する時期です。この地域差のつよい大形の祭祀土器 (大形壺と特殊器台) から小形祭祀土器 (小形丸底土器と器台) への統一は大和朝廷による全国統一の過程と対応しています。この第一段階の日常容器としての土師器の器形や組み合わせは弥生式土器のそれを踏襲しており、時代とともに装飾性、地域差の減少していったことが指摘できます。
第二段階(6世紀~7世紀中ごろ、関東の「鬼高」期) になりますと、5世紀中ごろに生産の始まった須恵器の影響を受けて土師器は大きく変化します。その大きな変化の一つは持ち運びのできる電が朝鮮から須恵器の製作技術の導入と相前後して伝わったことです。この電形土器の採用によって、煮沸土器としての甕は胴の長い大形のものとなりもまた把手のついた大形のものが、西日本一帯に用いられるようになりました。東日本ではその余波を受けて、住居の内部に固定的なかまどが築かれ、甑と甕が大形のものに変化している。この段階には大形の貯蔵容器は須恵器にとってかわり、壺は小型のものになあります。祭祀土器の矮小化も変化の一つです。須恵器の生産が後代までおくれた東日本では杯やなど一部の器形に須恵器の模倣がみられ、杯の一部は内面に炭素を吸着させたいわゆる内黒土師器がつくられています。これは水もれを防ぐ一種の釉薬の役目を果たすものであり、硬質の須恵器の代用品でした。
ほそう第三段階(7世紀後半~11世紀、関東の「真間」 「国分」 両期)に入ると、須恵器の盛行にともなって一時減少していた杯・高杯などの食器類がふたたび盛行し、新たに碗皿盤鉢類をはじめ有蓋壺などが出現し、土師器の製作が活撥になります。この現象は西日本における食生活の変化を示すものであって、金属製容器類の模倣あるいは木製高杯の模倣など食器類の大幅な変化が現われています。箸が食膳に上り始めたのもこの時期の現象と考えられます。奈良時代に入って畿内および西日本各地の須恵器生産が衰退し始めますと、相対的土師器の需要が増大し、量産化にともなって製作技術の簡略化が進行します。また、器種の減少や器の法量の縮小化を招来し、やがて奈良時代の終りごろには黒色土器を生み出すにいたるのです。これに対して須恵器生産の貧弱であった東日本、とくに関東以北では奈良時代においても前代の器形の組み合わせをそのまま踏襲しました。しかし、平安時代に入って、須恵器生産がようやく活撥化するにつれて、煮沸用の長甕と食器としての杯碗皿類に限定されるようになり、碗皿類の成形に轆轤が用いられるようになりました。
最後に土師器の変種としての黒色土器について若干述べておきましょう。
土師器の内面あるいは内外両面を俺で磨き、炭素粒を吸着させて漆黒色とした土器を西日本では黒色土器と呼んでいます。これには炭素の吸着方法によって内面のみを黒色化したものと、内外両面を黒色化したものとの二種があり、10世紀代に前者から後者へ、さらに11世紀後半代に瓦器に変化したと考えられます。畿内においては平城宮跡出土品にみられるように、8世紀後半代に出現し、その後しだいに増加して、9世紀から10世紀にかけて土師器三に対して黒色土器この割合で用いられているといいます。このような土師器の器面に炭素を吸着させた土器はさきに述べたように、中部山岳以東の東日本では6世紀代の鬼高式土師器のうちにすでにみられます。器形は杯・碗に限定されており、須恵器の代用品でした。東北では7世紀代に出現し、8世紀末から9世紀初めには両面黒色手法をとっており、両面黒色化は西日本より早いです。しかし東日本の内黒土師器や黒色土器は瓦器に転ずることなく、11世紀末にはふたたび土師器に戻っています。8世紀後半代に畿内において黒色土器の発生をみたのは、そのころから須恵器生産の衰退が著しく、土師器の量産化にともなって、その不備を補うために生み出されたものです。畿内の土師器には内黒手法の伝統はなく、東日本の内黒土師器を真似たものであることはいうまでもありません。この黒色土器は碗 皿類にほとんど限定され、若干の小形甕などがあります。東国では小形壺や耳皿などの器形もみられます。このような黒色土器は内面のみのものはいったん土師器をつくり、煤の多量に発生する燃料の上にかざしてつくったものと考えられますが、両面黒色の場合は窯を必要とします。
須恵器
須恵器は5世紀の初めごろ、朝鮮半島から新たにその製作技術が伝えられた灰色・硬質のやきものであり、平安時代まで約七百年のあいだ、土師器とともに用いられた最も普遍的な日常の容器でした。この須恵器の出現は大陸系の器種を含めて、日常の容器類を著しく豊富なものにしました。その器種は全時代についてみると六段階の消長がみられますが、東国ではさらにその後の段階まで製作されています。これらの全器種は用途別にみますと、貯蔵用の壺、甕、瓶の類、食器としての杯、高杯、、碗、皿、盤の類、調理具としての、擂鉢など各種鉢類、文房具としての硯、水滴類、祭器としての装飾須恵器や塔など、日常生活のあらゆる面にわたって豊富な種類を含んでいます。『古事記』 『日本書紀』 『延喜式』 などの古文献には、杯、盞、、、、、平瓮、罐、坩、甕など約五十種類の名称が記されていますが、実物との対比の可能なものはあまり多くありません。これ各種の須恵器をさらに器形別に分類すると百二十種類くらいに分類されます。しかし、それらの各器形が全時代にわたって一様に用いられたのではなく、一器種の生命には長短の時間差があり、また生活の様態や時代によって器形の組み合わせに変化があります。須恵器が全時代的に六段階に分けられるのは、その組み合わせの変化に基づいています。
初めに記したように、須恵器が土師器以前のやきものと区別される最も大きな特色は、還元焰による高火度焼成と、縦軸回転轆轤による量産的な成形技術にありました。しかしこのような進んだ技術を用いるためには、まず土師器以前の陶土より良質のものが選ばれねばなりません。土師器は主として集落に近い沖積層の粘土が用いられたと考えられますが、須恵器はその窯の立地からみて、より耐火度の高い洪積層および新第三紀層の粘土を用いています。つぎにその成形についてみますと、小形品では、一個ずつ轆轤による水挽き成形後、底部を俺で削って器壁を均一にする方法がとられました。大形品では、粘土紐を巻き上げて、内外から器壁を打圧してつくる巻き上げ法が用いられました。したがって古墳時代の須恵器には丸底のものが多く、台脚を有するものが多いです。また、轆轤技術の未熟さのため、壺、瓶などの器形は口頸部・胴台脚を別々につくり接合する方法が用いられましたが、8世紀中葉以降、一塊の粘土から多数の器物を引き出す水挽き技法が採用されるようになり、壺瓶類も平底 縦長の大形の器形がつくられるようになりました。須恵器の器面装飾としては、櫛や俺による平行沈線文、波状文、刺突文やまれに竹管文などが施されていますが、初期のものほど器面の各部にわたり、のちしだいに部分的となり、やがて無文化していきました。台脚の透かしも円形、三角形、方形 長方形などがありますが、初期のものほど大きく、各種の透かしが組み合わせて用いられています。
須恵器の焼成には丘陵斜面に構築された窯が用いられました。窯は長さ8~10m、幅1.2~1.5m、高さ1m前後の細長い、断面半円形のもので、丘陵斜面に溝を掘り、スサ入り粘土で天井や壁を貼った窖窯の形式に属するものです。床面傾斜は初期には15度前後の緩いものが多いですが、のちしだいに急傾斜になり奈良時代の終りごろには35度を超すものもあります。これは初期には初め酸化焰で焼き、一定の温度に達したのち、大量の薪を投入して焚口をふさぎ、窯内を還元状態にした燻焼還元焰焼成が行なわれましたが、のちしだいに高火度の還元焰焼成に転じたことを示すものです。したがって、初期のそれは器壁に浸透した炭素粒によって器面が黒ずんでいますが、6世紀以降には灰色からしだいに灰白色に近い色調への変化をみせています。
須恵器の生産は従来、5世紀中葉に大阪府南部の陶邑古窯跡群で始まり、地方の政治勢力を通じて一元的にその技術が拡散したと考えられてきましたが、最近では福岡県小隈古窯跡群のように5世紀前半代に遡る須恵器窯が発見されるなど、須恵器の発生が5世紀初頭にまで遡ることが明らかになってきており、朝鮮半島南部からの多数の渡来人によって多元的に日本各地で始まったと考えられるようになってきています。その後、六段階の変遷を経て平安時代まで焼かれたことは初めにも述べたところです。
その変遷の大要をみますと、大づかみには古墳時代と奈良・平安時代の二時期に分かれ、第三段階が両者の交替期をなしています。そのことを最もよく示しているのは杯・高杯などの日常食器類です。
丸底の浅い身に蓋をともなった蓋杯は7世紀末ごろ消滅しますが、それに代わって7世紀中ごろに出現した平底の、高台をもった新しい杯がその後の食器の中心をなしています。高杯も古墳時代には浅い怨形の身に台脚をもったものが基本的な形でしたが、奈良・平安時代には上部が平らな円盤状のものが用いられています。壺・瓶・甕などは球形ないし扁円形の胴から縦長の胴へ、そしてすべての器形にわたって丸底から平底への変化が最も大きな特色をなしているそこには生活内容の変化が大きな背景をなしていることはいうまでもありませんが、同時に大陸からの絶えざる技術や新しい器種の導入が行われていることも見逃すことのできない要因の一つです。
いまその変遷の大要を段階順に述べますと、まず第一段階(5世紀初頭~6世紀初め)は須恵器の工人たちの故地であった南鮮的な色彩の強いものから、しだいに日本化されたものへ変化していく過程であ日本各地に多元的に発生した初期須恵器はそれぞれ故地の技術によって異なる手法がみられましたが、5世紀末ごろ、大和朝廷の一元支配の強化によって統一的な須恵器が焼かれるようになるととも内からの供給が増加し、一部の地域では生産の衰退するところもみられるようになりました。この段階の特徴は高い立上りの蓋受けのかえりをもった蓋杯や太い台脚に大きな透かしをもった高杯、ロ頸部の太いなどにみられますが、古墳出土品には高杯型 筒型の種の器台や各種装飾須恵器などの祭祀的な色彩のつよいものが目立っています。
第二段階(6世紀中ごろ~7世紀初め)では須恵器の生産地がいつそうの拡がりをみせ、関東地方から九州までの各地において生産が行われている。この段階は各地において群集墳が形成される時期であり、古墳への副葬用の須恵器もさることながら、一般農民の生活のなかへも須恵器が浸透し始めた時期です。量産のために製品の粗雑化が目立ちますが、轆轤技術は進歩し、高杯の長脚化や壺瓶類の口頸部の長大化をもたらしています。この段階には祭祀用の器種は著しく後退し、新しく平瓶・ 台付長頸瓶台付盤などが出現し、第一段階との間に若干の器種の交替がみられました。また、東日本では細頸瓶が、東海地方では鳥鈕蓋付台付壺が、中国地方では鳥形瓶や環状提瓶など、地方色の出始めたことが注目されます。台付などはこの段階に新しく南鮮から伝わった器形です。
第三段階(7世紀初めごろ~同後半) はさきに述べたように歴史時代にむけて大きく変化した時代です。その基軸をなすものは仏教文化の伝来にともなって新しい生産技術が導入され、生活の変化に合わせた新器種がどんどん製作され始めた時期でもあります。この段階をもって消滅する器形には丸底の蓋杯、提瓶、直口壺、装飾須恵器などがあり、各器種とも台脚は退化して低い台に変化している。
第四段階(8世紀~9世紀初め)を迎えると古墳時代以来の器形はほとんど入れかわり、残存した器形も大きく姿を変えています。はこの時期をもって終わり、平瓶は扁平な胴に変わりました。新しく碗・盤鉢類が出現し、新型杯類と食器のセットを構成しています。とくにこの時期の後半に愛知県猿投窯で始まった灰釉陶器の生産は仏器類(水瓶・浄瓶など) を中心としており、各地の須恵器にもその影響をおよぼしています。祭祀用器物が、古墳副葬用のものから仏器へ入れかわったのです。この段階から須恵器生産の中心は大阪南部の陶邑窯から愛知県猿投窯へ移り始めました。それは古墳時代における陶邑窯の厖大な需要からくる過剰生産による生産の荒廃と、灰釉陶器を基軸とした猿投窯の生産の上昇という明暗二様の姿をみせているのです。
第五段階(9世紀始め~10世紀前半) は畿内を中心とした西日本における須恵器の没落期であり、猿投窯が須恵器生産を止揚して、灰釉陶器の唯一の産地として全国に供給を開始する時期です。しかし、北陸・関東・東北など東日本の後進地域ではこの段階からむしろ生産を上昇させているのであって、西日本ときわめて対照的です。
須恵器は東海地方から西日本にかけてはこの第五段階でほぼ消滅しますが、西日本の一部および北陸・関東以北の地域ではその後、11世紀末ごろまで生産が継続されたのである(第六段階)。
愛知県春日井市白山町高蔵寺 2・3号窯高蔵寺2号窯障壁部分陶邑窯高蔵寺68号