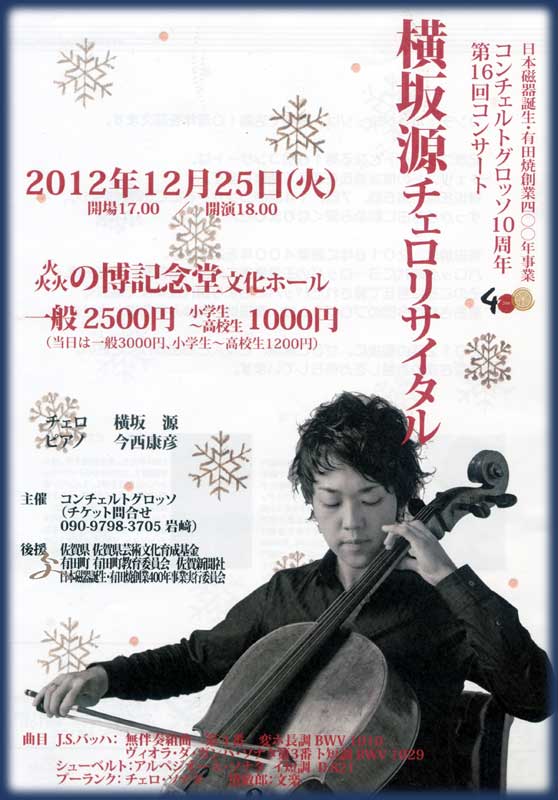唐津焼での焼〆とは、備前・信楽・丹波などの焼〆は長時間(数日間)窯を焚き続け、多くの投げ入れた薪の灰が器物に降り注ぎ、素地との融合で釉化し自然釉となるのと比べ、古唐津ではかまどや囲炉裏などの残った灰を土と混ぜ合わせて作った土灰などを器物に薄くかけて窯の中に入れ、窯焚きの幾分か薪の灰が掛かり焼〆になったのが多いようです。
その中で、薪の灰が多く掛かり景色が多くでているのを賞味がられているようです。
特に、唐津特有の叩き造りや板起こしで作られた庶民的な器具、種壷・すり鉢・片口などに見られます。
唐津焼〆とは
 陶芸のお話
陶芸のお話