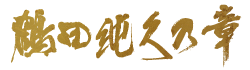- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
サイト:HISASIH-SHOP http://store.shopping.yahoo.co.jp/hisasihshop/
品目:斑唐津 碗形 茶碗
ytom074
◇寸法 長径:約15.2センチ × 高さ:約8.2センチ 重さ:約410グラム
◇この茶碗は熊川型の全面にわら灰の上薬を掛けた斑唐津の茶碗です。全体に卵色に発色し、見込み内外に部分的に焚き物の灰が掛かってやや青みが指しています。
◇土は砂毛の多い土を使い、縮緬皺・緋色とも抜群の土味がでています。高台脇にも焼成の時に薪が飛んだのか部分的に窯変しています。
◇使い込めばよく育つと思います。
◆◆◆予備説明◆◆◆
◇斑唐津(まだらからつ)とは、唐津焼では起源が最も古く、藁などの硅酸分の多い植物(主に稲科)の灰を混ぜた半透明の白い上薬で、土や焚き物の灰などがかかり釉面の溶け具合が斑状になり変化しているところより名前の由来があり、本来は普通の上薬でどれとこだわらない焼き物を焼くつもりでしたが上薬を配合する上で土灰の作り方に違いがあり木灰か草灰かどちらを主成分にするかで透明になるか乳濁かの違いでした。今日ではその乳濁釉の窯変具合が見所となっています。