織部焼という呼称は、今さら言うまでもなく、千利休の歿後天下第一の茶人として活躍した古田織部重然に因んでのもので、古田織部の好みという言い伝えによっています。
しかし、織部焼と古田織部とが実際にどのようなつながりを持ち、彼が作風を指導したとすれば如何ように行われたものか、その間の消息を伝える確かな資料は今までのところ見聞していません。
古田織部が茶人として活躍したのは、天正年間後期から元和元年(1615)に歿するまでがおよそ三十年間でしたが、当時の主要な茶会記に織部焼という言葉は見あたりませんので、おそらく江戸時代に入ってから織部殿のお好みという伝えによって、次第に人々の間に広まっていったものと思われます。
江戸時代のいつ頃から織部と称されるようになったかも判然としませんが、延宝元年(1673)に歿した片桐石州が「おりへ(べ)」と箱書付した香合、また「織部焼 手鉢 貞享伍年戊辰九月」(貞享伍年は1688年)の書付のある箱に収まった手鉢などが残っていますので、その頃にはすでに織部焼という呼称は数寄者の間で一般的になっていたことがうかがわれます。
織部とは其の壱 名称
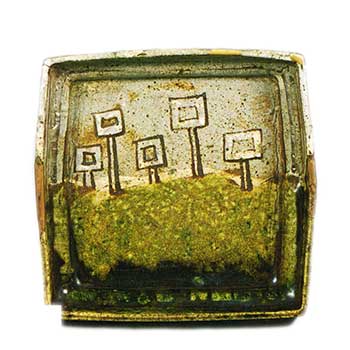 陶芸のお話
陶芸のお話


