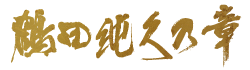織都黒 作品のほとんどは茶碗であり、黒釉を施した無文の茶碗で,瀬戸黒に歪みを加え、沓形に作られたものが多いです。
なかには黒釉の上に長石釉をかけたものもあります。
稀に茶入を見ます。
黒織都 織部黒に文様を加え、より強く装飾性の加わったもの。
これも主として茶碗が多いです。
黒釉を一部かけはずして白く抜き、そこに鉄絵具で文様を描き、上に長石土灰釉をかけ、黒釉の上には長石釉をかけた二重がけのものが多いです。
そのほとんどは、多く登窯で焼かれました。
織都(青織都)一般にいう織部は、白い胎土に鉄絵具で文様を描き、上に土灰を含んだ長石釉をかけ、さらに要所に銅を含んだ緑釉を施したやきものをさしています。
作品は多種多様で、窯により作調は異なります。
手鉢、叢物、皿、向付、徳利、香炉、香合などが最も多く伝世しています。
元屋敷の作品が優れています。
鳴海織部 いわゆる織部のなかでも、白土と赤土と継ぎ合わせて成形し、白土の上には緑釉、赤土の上には白泥や鉄絵具の線描きで文様を描いて長石土灰釉をかけたものを俗に鳴海織部と呼んでいます。
手鉢、角鉢などに多く、轆轤びきされた沓茶碗や瓶形の水指も作っています。
鮮やかな緑釉と、淡い赤色の対象が美しいです。
鳴海織部の語源は詳らかではありませんが、あるいは鳴海絞りと色調が似ていることによったものかもしれありません。
赤織都織部の一手で、赤土を用いて成形し、白泥と鉄絵具の線描きで文様を施し、一部に緑釉をかけたものであります。
向付、香合、茶碗などに多いです。
総織都器全体に緑釉をかけたものをいいます。
釉下には線刻や印花によって文様が施され、なかには釉を白くかけはずして文様をあらわしたものも見られます。
皿、鉢、香炉、香合、猪口が焼造されていますが、茶碗はほとんど作られていません。
志野織都志野と同じ技法で作られていますが、登窯による量産体制に入ってからのもので、穴窯の志野のような柔らかい質感と雅味がなく, 釉がよく溶けて膚に赤みがありません。
鉢や向付などに多く見られます。
享保年間Kはすでに「シノオリベ」と称されていました。
唐津織都 元屋敷や高根などで唐津と似かよったものぷ焼かれています。
それを唐津風の織部焼という意味から唐津織部と呼んでいますが、作品は極めて少くありません。
美濃伊賀伊賀焼と似た作振りのものが美濃の元屋敷や大平の窯などで焼かれていますが、それを美濃伊賀と呼んでいます。
器表の一部に白濁色の長石釉をかけたり、一部に鉄釉を点ずるなど、かなり細かい技法を示しています。
織部とは其の五 種類
 陶芸のお話
陶芸のお話