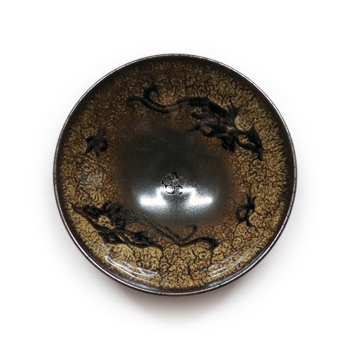焼き物(陶磁器)の話の中で焼き締まるという定義は中々難しい話で、理解している方は多くないと思います。
焼き締まるとは高温で焼成すると冷えて堅くなる。と、単に言ってしまえば簡単なのですが、土器の時代から現代のニューセラミックまでの焼き物の歴史を考えるとそう簡単ではないのです。
そこには科学的な考えや物質の成り立ち等を考え理解しなくてはなりません。
まずは、高温で焼成された物質はどうなるか?その物質はどんな物があるのかを知る必要が有ります。
焼き物で一番必要な物はSiO2、二酸化ケイ素(にさんかけいそ)やシリカ、無水ケイ酸、ケイ酸、酸化シリコンとも呼ばれます。地球上で最もポピュラーな物質で、地殻を形成する物質の一つとして重要です。
このSiO2を高温で焼成し溶かして他の物質と合成させるかが焼き物の歴史であり成り立ちです。
SiO2と言えば硝子の原料でも有りますが、ガラス化という言葉を使いますが、高温で溶けてドロドロの状態なのですが火山噴火活動している溶岩がその状態でSiO2がその状態です。
その他物質にはAl2O3の酸化アルミニウム、Na2O・K2O・MgO等のアルカリ性分などがあります。
SiO2を溶かす(よりガラス化させる)役目のアルカリ性分、骨格の役割の酸化アルミニウムとこの3つの物質が混ざりあっているかが重要で、混ざり具合でガラスだったり陶器や磁器、ニューセラミックになったりします。
それに温度が重要で土器は800-900度位で須恵器は1000-1100度位で陶器や磁器は1200-1300度位でニューセラミックは14000度位です。
それ相応で焼締める土を使っているようです。
陶磁器などは焼締まる土で形状を造り、表面がザラつくのでガラス状態になる釉薬でコーティングするというふうになります。
なぜこんな感じで「焼締まる生地」としつこく言うかというと、逆に焼締まらない生地がどうなるかというと、まず吸水性が高くなり水分が乾かなくて湿気が保持されます。そのことで虫や菌類・細菌などが温存され不衛生になります。
酷くはウイルス感染などを引き起こし疫病が蔓延します。それは古今東西を問わず世界各国で実例があります。
歴史的に見ると陶器が量産されるようになると、その造りやすさを重視しカオリン質を優先し焼閉まらなくなっています。又、機械化が進むとカオリン質は重要でなくなり磁器質の焼締まる磁器製の焼き物が多くなりました。
こんにち、手作りを目指す陶芸家が気を付けなければいけないのは造りやすさを重視しカオリン質の高い土を使うことで焼閉まらない焼き物になりがちです。造りにくい土、可塑性がない珪石分が多い土で如何にして造るかが古より伝わる技法ともいえます。
それでは焼けた焼き物が如何に焼閉まっているかを確かめる方法としては
・釉薬(薪窯の灰も同様)が掛かっていない生地土に水滴を落とし水面張力で丸くなった状態が10分保てばOK、保たなければ改善の余地ありです。
・焼けた食器を長く使っていて黒くならない土を使うようにする。もしくは、焼成に気を付ける。
黒くなるのは湿気などで黒カビが発生し、それが残った物と思われます。貫入のなかの茶渋とはちょっと違うかも。
・時々20倍位のルーペで除いて確認する。普通じゃ見えない小さな虫が見えます。見えなかったらOK。虫がいると言うことは菌も発生・温存している事と言えます。
もう一度、土の概念を改めて観ることも必要ではないでしょうか?