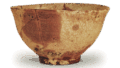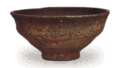高さ:7.5~8.3cm
口径:14.3~15.0cm
高台外径:5.8cm
同高さ:0.8cm
『大正名器鑑』では、昔、堺に「かいふ屋宗節」という茶人あり、粉引きの名碗を愛蔵していた。この伯庵もその宗節の所持であったかと推測しています。ただし、宗節がいかなる茶人であったかはつまびらかにしていません。また同書には数点の伯庵の名器が紹介されていますが、この宗節伯庵が本歌の関戸家の伯庵に、形姿最も近いのでぼないかと思われます。
まず素地は高台のところで、かすかに黄味を帯びた灰白色を呈し、いくぶん堅く焼き締まっています。高台は削り出しで、速い轆轤(ろくろ)で端正にひかれ、よく締まった竹の節高台になっており、高台わきの削りあともあざやかです。伯庵の高台は、普通、三日月ふうに片薄の輪状であることが約束とされていますけれども、どこでは片薄ではなく、ほぼ正しい輪状になっています。
轆轤(ろくろ)はのびのびと、少し速めの速度で、回転のあとが快い轆轤(ろくろ)目となって器面を右上がりに走り、そして、その一部にかなりはっきりと素地のひび割れがあります。口縁はゆったりとひずみを見せながら、少し歌分り気味になって広がっています。そのため常の伯庵に比べていくぶん平たく見えるようです。見込みは容量豊かに、ことに轆轤(ろくろ)目の大きなうずがいちじるしいです。この際その轆轤(ろくろ)目の一部と外側のひび割れが一致しているのは注目すべぎであって、この横ひびは成形の際に、内外の圧力の不調和によって生じたものと考えられるのです。つまり陶工の轆轤(ろくろ)のそういう手癖から、このひび割れが生まれたといえましょう。
釉薬は透明で光沢のある、いわゆる黄瀬戸釉がたっぶりとかかり、高台の飛び込み釉も約ぴわ束どおりです。釉調は、全面に大小の貫入があり、色はかすかに枇杷色を帯びる程度で、だいたいは室町時代の黄瀬戸によく見るものと酷似しています。とくに見込み茶だまりの部分は釉層厚ぐたまって、落ち着いた緑色が美しいです。そしてまた約束のごとく、外側一文字のひび割れのあたりから、なむひ調のかっ色齢釉が濃淡ひらむらと幕状に流下してい吃わらばいこれは窯中ひび割れのところから破れるのを防ぐため、鬼板に藁灰などを混ぜたものを厚く充填し、その上から施釉して焼いたのが、こうした景色を生んだのであって、これに似た法はすでに朝鮮李朝の陶工がしばしば用いているところです。
伝来は『大正名器鑑』によれば、はじめ宗節所持、のちに土屋相模守あるいは大文字屋宗積のいずれかに移り、文政のころから溝口家の所蔵となっていたのが、明治三十四年ごろ、高橋帯庵に譲られ、さらに大正九年ごろにいたって現所有者に割愛されています。
なお、『東都茶會記』には、井上世外侯が大正二年十月、金沢の客十五人を内田山に招いた際、本歌の伯庵に、さらにこの宗節伯庵を重ねて、二服に点て分けるという豪華版を演出し、加賀の茶人連を驚倒させたと伝えています。このことは宗節が本歌に比肩し得る名碗なることを如実に物語るものです。
付属品は、とくにあげるほどのものはありません。
(藤岡了一)

伯庵 茶碗 銘宗節 008


高さ8.3cm 口径15.0cm 高台径5.8cm
伯庵茶碗のなかでは本歌伯庵、奥田伯庵などとともにもっとも作振りの優れたものの一つでしょう。見込の広い重厚な椀形の姿は、関戸家の本歌伯庵によく似ています。轆轤はのびのびとして口は端反りぎみに開き、高台は端正に削り出され、よく締まった竹節高台になっているが。伯庵の約束の一つとされている片薄高台ではません。外側一文字のひび割れのあたりから、なまこ調の飴釉が濃く薄くなだれ、全体に厚くかかった黄釉は透明によく溶けています。全面に大小の貫入があり、色はかすかに枇杷色をおびた黄釉であります。高台の飛び釉は約束通りで。黄味をおぴた灰白色の土膚はいくぶんかたく焼き締まっています。
「宗節」の銘の由来は判然としないが、おそらく昔、宗節なる茶人が所持していたのでしょう。後に土屋相模守、あるいは大文字屋宗積のいずれかが所持、文政の頃から溝口家の所蔵となり、明治三十四年頃高橋希庵に譲られ、さらに大正九年頃にいたって現所有者の蔵となったものであります。
宗節伯庵 そうせつはくあん
名物。伯庵茶碗。
文政(1818-30)以後は溝口家にありましたが、その後高橋篇庵を経て住友家に入りました。
(『大正名器鑑』)