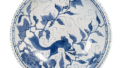急焼 キビショは茶を沌ずるのに用いる小器。壺形で蓋・注口・把手を備えます。
古くは金属製のものも使われましたが、後世は妬器製・陶器製・磁器製などのものがもっぱら用いられて今日に及んでいます。
【名称】キビショウ、キュースなどとも呼ばれ、急須 きゅ一すは今日最も広く使われるが、左記の語はいずれもキビショを示すものであります。
茶壺(『界茶賤』『茶疏』『陽羨名陶録』『真斎清事録』)、若壺(『間情偶奇』)、茶瓶(『会典』『煎茶仕用集』『清風瓊言』『芸苑日渉』)、若瓶(『資暇録』)、茶甑(『良山堂茶話』)、茶注甑(『茶疏』)、茶注(『煎茶式』)、若注(『煎茶式』)、茶銚(『煎茶式』)、砂耀(『類書纂要』『煎茶略説』)、宜興鍍(『陽羨名陶録』『荼薩堂雑録』)、急焼(『煎茶略説』『蔓薩堂雑録』)、急備焼(『芸苑日渉』『本朝陶器放証』)、急尾焼(『石山斎茶具図譜』)、急火生(『臨時客応接』)、急子(『守貞漫稿』)、急注(『志濃廼舎歌集』)、急須(『煎茶式』)。江戸時代の文献をみますと、初めは茶瓶の字を当てたがそれがどのように訓読されたかは不明。しかし末期以降はキビショの語がもっぱら使われ、『芸苑日渉』に急備焼は急須であると出ますと、『良山堂茶話』『他山石』などがその説にさらに明の『三余贅筆』の急須の文字を付会して、以後キュースの語と共にキビショはキュースの転誂であるとする説が長く行なわれました。
しかし明治末期に至り、言語学上からキュースこそキビショの転誂であることが明らかとなり、キビショは台湾土語のキプシオまたは南方語のキビシュと相通じるもので、共に中国音より変化したものであると説かれるようになりました。
『東京人類学会雑誌』明治四十三年1月号および4月号に、小川尚義・山田孝雄・山中笑の諸家の論説があるから参照。「起原」中国における陶製キビショの起原は、明の万暦年間(1573I1620)宜興の金沙寺の僧がつくったのに始まるといわれますが、わが国においてもキビショが使われたのは江戸時代であります。
その時期は一説に煎茶道の始祖といわれる石川丈山の時代にまではさかのぼらず、『蔓茜堂雑録』に「高芙蓉キビシャウを検出し宝暦六年大雅堂之を上木印施す」とあるのを引いて1756年(宝暦六)以降とするものが多いようです。
しかし『近世崎人伝』巻二の売茶翁茶具図に中国製キビショの図があることからすれば、1756年(翁すでに八十二歳)以前から使用されていたとみなすべきであるでしょう。なお1756年刊の『煎茶仕用集(青湾茶話)』に磁瓶で茶を沸かす記事があります。
しかしあまり広く行われなかったことは、例えば1807年(文化四)刊の『東海道中膝栗毛』第六編に淀川の川船で乗り合わせた隠居の急須を喜多八が尿瓶に間違えた滑稽談があることからもわかるであるでしょう。「使用法」キビショは売茶翁茶具図にみられるように、初めはもっぱら直火にかけたようであります。
『煎茶仕用集』『清風瓊言』『臨時客応接』『守貞漫稿』『他山石』などの記事もまたこれを証します。
そして特に塩炉上で用いられたのでコンロキビショの名で呼ばれることもあったことが『螺客三体誌』『耳敏川』などにみられます。
このコンロキビショは把手がまっすぐで横に出た形(横手)のものですが、化政期(1804-30)の俺茶流行時に至って、把手が湾曲し後に付いた形(後手)でもっぱら茶を俺ずるのに用いるダシキビショが使われるに及び、従来のコンロキビショはユワカシと呼ばれ、ダシキビショだけが単にキビショの名で呼ばれました。
しかしその後コンロキビショでありながら直火にかけず単に茶を俺ずるのに用いられるものが出て、コンロキビショとダシキビショとを区別する理由がなくなり、いずれも単にキビショの名で俺茶に用いられるようになりました。
【製作】キビショの製作は、宝暦(1751-64)の頃煎茶道中興の祖売茶翁の在世当時に、京都建仁寺近傍の三文字屋七兵衛(三七)と清水の梅林金三とが始めたといいます。
また寛政(1789-1801)の初めに村瀬拷亭・上田秋成などが図って清水の六兵衛にっくらせたともいいます。
この六兵衛については、『煎茶略説』『屠赤瓊々録』がその極めて妙手であったことを伝えています。
その後煎茶道の隆盛に伴って木米(左兵衛)・嘉助・与三兵衛・周平らの名工が輩出し作品も世に重んぜられましたが、特に木米と事を共にした岡田久太の作品は使用が快適で好評を博したといいます。
『屠赤瓊々録』『耳敏川』によれば、上田秋成のっくったキビショが世にもてはやされ、粟田焼のキビショはこの創製に基づいていることがわかります。京洛以外でキビショをもって有名な者には、天保年間(1830-44)における万古焼の森有節かおり、わが国で最初に急須型作り法を発明しました。
万古焼のキビショはその後特殊な提灯型を用いて廉価生産の方法を確立しその販路を広め、明治期を通じて長く行なわれました。
また常滑の杉江寿門が安政(1854-60)の初めから白泥・朱泥の急須を焼き始めましたが、1878年(明治一二清人金子恒について教えを受け、わが国で初めて宜興風の朱泥急須をつくったといいます。
「形質」『煎茶略説』には「急焼も唐製をよしとす、然れども其中に好悪あるようで、中にも最上の品は高翁所持の急焼南瓜形(唐物)清水六兵衛模型して世上に売茶翁型といふはこれなり、此外広東急焼(俗に紅毛型という)宝珠形(新渡急焼の写し)其外朝鮮形、南蛮形、広口などいふは、それぐよりどころあるようで、仮になづくるなるべし」とあります。
『若壺図録』には「形状一ならず。或いは円、或いは方。或いは稜、或いは匠。或いは平、或いは直。或いは崇く、或いは卑し。或いは大、或いは小。しかして蛋の如きものは円からざるを得ず。斗の如きものは方ならざるを得ず。触の如きものは稜ならざるを得ず。鼓の如きものは謳ならざるを得ず。砥の如きものは平らかならざるを得ず。篇の如きものは直ならざるを得ず」とあるようで、また式様として小円・菱花・水仙・束腰・花鼓・鵡蛋以下二十有余を列挙しています。
このようにキビショの形状は多種多様ですが、その要は容量・蓋・注口・把手のいかんにあります。
近頃はもっぱら磁器質・陶器質のものが使われているが拓器質のものがよい。宜興の茶壺は妬器質のもので施釉はなく、その土色に従って朱泥・紫泥・白泥・鳥泥・黄泥・梨皮泥・松花泥などと呼ばれます。わが国では常滑や佐渡の常山の朱泥が有名ですが、いずれも明治以降に発達したものであります。
なお宜興の茶壺には詩句・古語・姓名・別号あるいは堂・亭・斎・館などの款識があります。
最後に現代の煎茶道におけるキビショの用語例をみますと、コンロキビショに当たる横手のものをボーフラと呼び、無釉粗質の白泥で湯を沸かすのに用い、形はやや大きいです。ダシキビショに当たる後手のもの(横手のものもある)は単に急須と呼び、妬器・陶器・磁器など種々のものがあって茶を俺ずるのに用い、その形は小さいです。