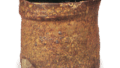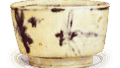大和国(奈良県)赤膚焼の陶工。
もと京都清水の工大。
寛政年中(1789-1801)に郡山藩主に招かれて伊之助という者と共に来て住み、赤膚焼の再興に従事しました。
まず土を五条村(奈良県五条市)から取り、黄土に赤斑があって粗いものと白土とを用い、これに灰白色の釉を施し、さらに黒斑の釉を加えて長門萩焼に類するものをつくり、「赤ハタ」または「赤膚山」の銘を付けて世に出しました。
前者は藩主柳沢保光(尭山)から受けた印、後者は自己がつくった印であります。
子孫が業統を継ぐ。
(『本朝陶器放証』『日本陶工伝』)※あかはだやき