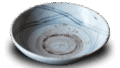古墳時代以後につくられた褐色系の色を呈する素焼の土器弥生式土器の後身であり、のちにかわらけとなって系統的には現在まで続いている。総体的にみると、ほぼ並行して用いられた須恵器に角張った感じの器形が多いのに対して、土師器は丸味を帯びているのが特徴である。土師器という名称はもともと土師、すなわち土器の製作工人がつくった器という意味であって『延喜式』によったものである。『延喜式』によると、調として土師器を貢納する国は大和(奈良県)と河内(大阪府)の二国で、大和には鍋を貢進したものと、玉手土師というものと土師というものとが、またにえのはじつきつくりのはじはじのむらじ河内には土師というものと坏作土師というものとがあったことがわかる。ところが『日本書紀』雄略天皇十七年の条には、土師連らが「御膳盛るべき清器」を奉るように命じられた時、六ヵ国から私の民部を奉って、これを蟄土師部と呼んだととが記されている。この内容が事実かどうかはわからないけれども、土師部が古墳時代の赤焼の土器の生産に関与していたことは間違いなかろう。
しかし土師部の工人が製作した土器はごく一部であったと推測されるので、一般に土師器と呼ばれるけれども、それは土師部の工人がつくったと推測される土器およびその前後の時代を含めて、これと同種類の土器を指している。土師器からかわらけへの変化をどの時点に求めるかはまだほとんどわかっていない。土師器は弥生式土器の後身であるから、その製作技術も弥生式土器のそれを継承したものである。粘土は少しは精製されたのではないかと思われる弥生式土器に比べて、大きな砂粒の少ないものである。細砂混じりの比較的緻密な胎土のものがある。粘土紐をつくり、巻上げの技法によって成形するのであるが、田中琢によると成形に三種類の手法が確認されている。一つは植物の大形の葉の上に粘土紐の中心から左廻りに巻き上げていく方法であって、大形で平底のものに用いられ、第二は右手に持った粘土紐を、左手の上で中心から左廻りに巻き上げる方法で、第一の手法で成形するより小形のものをつくるのに用いられた。第三は上面が球状に凹んだものを型として、その中で底部をつくり、その上を左廻りに巻き上げて成形する手法で、主に壺や甕などの深い丸底の器形をつくるのに使われている。成形の第二段階として器壁を薄くするために、粘土を箆で削ったり、余分な粘土をかき取ったりしている。その痕跡の刷毛目が顕著に残っている。ま表面を密にするために箆で磨いたり、おそらく湿った麻布でなでたりして調整している。浅い器形には磨きの要領で連弧状・放射状・螺旋状の文様を描いたいわゆる暗紋をもつものがある。土師器の窯跡はまだ発見されていないが、製品から推定して八〇〇度前後の温度で、酸化焰によって焼いたものと考えられている。土師器が成立したのは畿内か瀬戸内かまだ明確でない点が多いが、原口正三が発掘した大阪府松原市上田町遺跡の層位は重要である。この遺跡では三層が識別され、最下層は畿内第五様式の弥生式土器を出土し、第二層の土器では壺や甕が丸底になり、内面を削外面に刷毛目調整を加えて器壁を薄くつくってある。これは土師器に特徴的な成形法によってつくったものである。第三層からはほぼ四世紀後半に当てられる布留式の土師器が出土した。この遺跡で認められる土器の変化に基づいて原口正三は土師器に特徴的な丸底の出現を畿内が瀬戸内より一歩早かったと考えている。土師器の器形は、弥生式土器の器形のセットを受け継いで壺・・高杯を基本的な構成要素とするもので、これに土師器を特色付ける小型丸底壺がある。須恵器の製作が始まると小型丸底壺が消滅して、須恵器の影響を受けた怨・などが、また須恵器の形をまねた各種の器形もつくられ全般的に大きな影響を受けた。貯蔵用に適した須恵器に対し、土師器は煮沸用として鍋や甑の類が発達することになった。しかし日常生活において土師器が主要な容器であることは変わらなかった。平城宮跡の763年(天平宝字七)頃と推定される一土坑内から発見された四〇一個体の土器にみられる比率は、土師器が八三パーセントで圧倒的に多く須恵器は一七パーセントにすぎない。土師器の中では煮炊きに使う甕・鍋・かまどが一一・四パーセントで、食事の際に用いる椀・皿・杯・盤・高杯が八七三パーセントと大部分を占め、このほかに貯蔵用の壺が若干ある。普通の住居跡では煮炊きのための器が食器より多くて、平城宮における食生活が特異なことを示しているけれども、普通の住居跡においても須恵器より土師器が多く発見されている。
世紀後半から九世紀にかけて、土師器の製作技術をできるだけ簡略化しようとする傾向があり、同時に器形の種類が減少しまた器が小さくなっていることが認められている。これは新しい技術を導入せずに量産を行なおうとした結果と考えられており、この保守的なあり方から抜け出そうとする動きの中から成立したのが黒色土器と瓦器だという。このほかに土師器の系統に属するものとして、特殊な用途のため早くから分離して独自の発達をとげたのが製塩土器である。擦文土器は北海道においてほぼ奈良時代の頃に行なわれた、内外面に刷毛目の顕著な土器である。擦文というのは刷毛目文のことで、土師器の強い影響を受けて成立したものである。なお土師器との関連はないが、文土器とほぼ同じ頃から平安時代に並行して、北海道の東北辺から千島・樺太、すなわちオホーツク海に面した地域で行なわれた独特の土器があって、オホーツク式土器と呼ばれている。赤褐色または暗褐色で深鉢や壺形の土器が多く、種々な文様で飾られている。文様の手法では、液状に溶い粘土を管を通して貼り付けた細い浮文が特徴的なものである。(横山浩一「土器生産」近藤義郎・藤沢長治編『日本の考古学』古墳時代下田中琢「(古代・中世における手工業の発達窯業)畿内」三上次男・楢崎彰一編『日本の考古学』歴史時代上並びにその引用文献原口正三「大阪府松原市上田町遺跡の調査」『大阪府立島上高等学校研究紀要』復刊三玉口時雄「土師器」『新版考古学講座』五)
弥生式土器の系譜に属する赤褐色の素焼き土器は、古墳時代にも引き続いて生産されました。
古墳時代から古代にかけて作られたこの種の土器を土師器と呼んでいます。
一般に、丸底が多く装飾に乏しいですが、古い土師器は小さな平底で、器表を櫛目文などで飾ることも多く、弥生式土器との区別は容易ではないようです。
器形には実にさまざまな大きさ、種類があり、その用途も水や穀物の備蓄用のもの、煮炊きする料理用のもの、祭祀用のものなど多岐にわたっています。