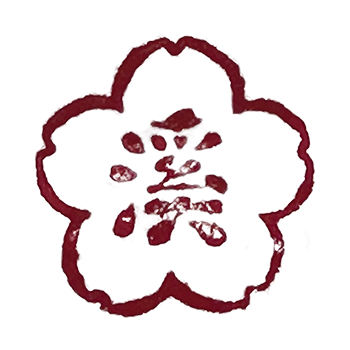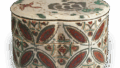嬉野氏
藤津の莊嬉野は、正曆五年(995年)大村直澄が彼杵、高木、藤津の三莊を支配せし當時の領地にて、以前は其支族の大村氏を能古見に配し、嬉野氏を嬉野に居らしめて東西の兩鎮とした。抑も嬉野氏の祖先は、藤原鎌足十三世摂政関白太政大臣教通より出でしものにて崇徳天皇の大治年間(1126-1131)教通五代の孫藤原幸通肥前権守に任じて養父の綾部城主となり、二條天皇の平治元年(1159)肥前の總追補使と成ったのである。
其子日向太郎通良亦同じく總追補使となりて神崎領せが、當時の権柄清盛に叛き、永暦七年(1167年)平家方の將平家貞と戰ひ死して梟首された。其子通盆に至つて後鳥羽天皇の文治三年(1188年)杵島莊白石を領し、之より代々稲佐郷の地頭職となつた。それより六代白石六郎道恭(贈従四位)は龍造寺季盆、草野永等と共に弘安の外寇と戰ひ、偉勳を奏して嬉野を併領するに至ったのである。
宇禮志野を姓とす
通恭より七代越前介通臣は文中三年足利勢と戰ひ死し、其子彌太郎通晴は、藤津莊宇禮志野に居住して姓となし宇禮志野祐三と称した、曾孫通久に至り高來の領主有馬仙巖の旗下となりしが、彼は領内大草野に十六善神を經營し或は河瀬に寶積寺を建立した。そして亦元文年間權現山に築造せしものが湯之田城である。其子通盆の時龍造寺隆信に属し宇禮志野を嬉野に改めしといはれてゐる。嬉野系岡左の如くである。
別派の嬉野氏
然るに嬉野系には又別派ありてそれは高來の有馬治部大輔澄通の後裔萬五郎通次なる者、有馬氏の旗下さして宇禮志野治郎少輔と改め、南袴野、宇土手、河瀬、庭木、神六、小田志大草野及び北南今川より西五百三十町を領有して天正元年九月八日卒し、長子刑部大輔通治又同じ岩屋の城主なりし云々との一説がある。
而して前記の嬉野氏が支配せし範圍も亦吉田、宇土手 河瀬、庭木、神六 小田志、大草野、今川に及び、天正四年九月九日嬉野直通(通稱通治とあり)は、柄崎の後藤貴明と戰ひ嬉野下宿に於いて戦死せし稱せられ。有馬系の通治は同六年十二月後藤貴明と岩谷城外に戰ふ云々と傳へられて、何れが正當なりや精しくはなほ考可であらう。
嬉野焼の區域
今茲に嬉野焼として記述するものは、前記の如く杵島郡の東西川登と、藤津郡の全部を指せ各山である。東西川登地方は後藤氏の領域なるも、時折兩郡領主の争奪地なりしが如く、而して此處の内田、袴野、弓野、庭木、小田志の古窯品か、全く武内と相似たるものあるを以て、畢竟後藤家信に從ひ來りし韓人の分布なりの説は肯定の價あるも、此地方が奮嬉野領であり且嬉野焼の開窯中には尚頗る往時に渉れるものあるを以て、特に藤津系として記述することにせしものである。
杵島郡部の古窯にては東川登の内田を最古とし藤津郡部に於いては塩田の大草野と、嬉野の不動山を以て最古の開窯せらる。而して之を地理順により杵島郡より記述せんに、東川登は南北朝時代既に相當の集落をなせしもの如く、袴野の貴船神社の石鳥居などは村社としては見る可き建造物であり、そしてそれには元享元年(1321年)後藤兵庫頭光明(武雄十一代の領主)祈山刻まれてある。
内田の皿屋
永野の内田の古窯地は武雄より一里二三丁にて、此處の高麗神と稱する韓人墓は、街道より四丁許り横の谷奥なる皿屋谷にある。其嘘の奥山家の脊戸を登れば、山腹に高さ三尺餘りの長方形自然石が建られてあり、その頭部が烏帽子形に斜に成ってゐる。
内田高麗神の碑考
碑面の右方は寛永元年(1624年)と記され、左方には十月二十日施主敬白と記されてある。そして中央なる奉の字の下に「建立ス池春石升已禪定尼伏詐若祖也(不明の字多し推讀也)とあるが、禪定の銘あるは婦人なるべく、或は文祿慶長の朝鮮役後に渡せし韓人の妻であらう。此處の窯跡には既に一と抱へほど成長し梨樹あるを見れば、相當の年代を經しに相違ない。
川登内田の古窯品
此古墳は元谷奥の頭にありしを、其處に溜池を築造する際浦川榮作なる農人が、我家の脊戸山に移せしものである。此山裾が古窯の窯頭に當ると覺しく、此處の竹林を漁れば薄青地や、灰色釉又は鶯茶釉飴釉、黒茶釉、赤茶釉、飴釉等の茶碗や小皿があり。小皿には深形や形及突底があり、總て高台の無釉部頗る弘く、中には蜷尻のものも雜り、或は縮緬の生せしものもある。
又飴色釉や灰色釉の七寸皿にて、ゆりの廣線に蹴猫にてギリを廻はし、底には二三本芦を描きしものや、又茶碗や小皿には厳ともつかぬ草の穂先を曲げし如き拙な鐵描があり。或は薄飴釉の八寸皿に得体の知れぬ草の如き模様がある。そして凡てに於いて頗る元始的な作風である。
忠平谷
内田の忠平谷に於いて、此地數人の農家が合資を計り、有田稗古場の元窯焼中島忠作を招聘し、此地(今東川登村役場の裏)をして五六間の登窯を築造し、有田や小田志より工人を招きて磁器を製せしものにて、原料は天草石を用ひ、製品には捺染型打染附の火鉢、丼、皿、鉢、平碗、花立等凡て下手物を製造し、伊萬里市場にて販賣せしが、四五年にして廢窯したのである。
袴野甕屋
前記內田皿屋の分窯が袴野の甕屋谷といはれてゐる、蓋し此處は全く石器質の甕のみを製作しが如く、採掘すれば其破片のみが現出する。此處も相當の年代を經しことは、當時の窯江口勘右工門の墓に正保五年とあり、此江口系が又弓野に分窯して其處にても甕を焼いたものらしい。以上が東川登村にある古窯地で現在製陶する者は皆無である。
弓野山
次は西川登村の弓野山である、此處は今八十戸の村落にて、寛永年間前記の内田及袴野より分窯せしといはれてゐる。古窯品には栗色地に白化粧を掛け鐡釉にて繪刷毛をし、それに青藥を流せし大皿があり。又白化粧地に松を青薬に盛り、技幹のみ鐵描にて面白く文せる水甕などは、全く武雄系の川古の谷と同技工にて、又之が筑後國三池の二川焼に摸寫されてゐるのである。
庭切擂鉢
而して此地の製品は幾許もなく、甕や擂鉢などの下手物製作に移りしもの如く、今庭木や小田志の如き技巧品の殘缺が頗る乏しき所以である。其當時より庭木、小田志よりも格式一段下位にありしことは、同じ擂鉢製作に就いても小田志物には高台造りありしに封し、弓野物には庭切と稱して高台附を赦されず、乃ち糸切でありしなど、如何にも藩制時代の階級的區別のさまが窺ばれる。
弓野の目茶漬
隣地神六山の磁石が発見されしより、有田の製磁法に做らひ薄鼠色の軟質磁器を製造した。それは重に目茶積と稱し反形碗の底を蛇の目に剝釉して重ね積をしたのである。此時從來の古窯の外に上窯が出来、次に下窯が築造されたのである。斯くて天草石使用發見より之を神六の地土と混用することゝなり、一時非常に盛業を極めしも逐年衰退して轉業する者多く、まさに明滅の境地にあったのである。
江口龜次郎
愛に筑前福岡大名町なる原田卯右工門の次男龜次郎といへる者、博多人形の細工師藤原清重に入門して其技法を學びしが、後年田舎廻りの細工師として放浪の末、藤津郡吉田山に漂泊してゐたのである。折柄弓野の中村佐平、中尾文左工門の二人が或動機より龜次郎を弓野山へ同伴せしを、奥川權左工門之を自宅に招き、始めて造らせしものが今の弓野人形の濫觴にて、是れ實に明治十五年であつた。
弓野人形
明治二十年龜次郎は、江口友三郎の養子となりて江口姓を嗣き其子又次郎と稱してゐる。爾來此地は全く土偶の製造地となり、龜次郎の外六戸の同業者がある。近來此技漸く世に現はるゝに至り、本縣蓮池出身なる江崎利一の大阪グリコ製菓より大量の注文があり、今や佐賀縣唯一の郷土人形として發展の機運に向ひ、現今同業組合を組織し中島弘義(有田工業學校第六回卒業)其組合長として斡旋しつゝある。
龜次郎の頌徳碑
近年大阪其他より多くの注文に接し、年産額三萬餘圓を撃てゐる。土偶製造の原料としては、東川登村の永野及び中通村鳥海の粘土を使用してゐる。昭和七年二月二十九日此地の同業者は、此人形製作の創始者江口龜次郎の頌徳碑を弓野の東口に建設したのである。
弓野人形の作風
弓野人形は元來博多系なるも彼れの文化的作風なるに反し、此處のは多く古典的なるローカルカラーを發揮してゐる。作法は殆んと押込型にて、五寸以上の製品には底部に紙を貼りてあるなども全国に類がない。種類は玩具類福神、貯金玉、床置、假面、神佛像等頗る廣汎である。就中龜次郎作の花魁土偶は尺除もありて變形態振った作風を顕はし。古瀬與三郎作の踊子供、清正馬乘なご稚氣掬すべきものがある。
内田皿屋の韓人か、或は別に渡來せし韓人かは不明なるも、西川登村なる庭木と小田志に分窯し殊に萬治、寛文頃より元祿時代まで盛んに製陶されしが如く、今此兩山の古窯趾多きを見ても察するに徐りある。然して庭木、小田志及び前記弓野の三山は何れ同系の分窯せしものであるらしい。
庭木山
庭木は元百五十戸の戸數ありし由なるも、今は百十餘戸に過ぎぬ。此處の古窯趾としては、河内口(庭木甕屋ともいふ)より奥に涉り祖頭先、芋母口、梅木原根地、新山、土井木原、八人塚、板屋窯の谷、板屋物原上、板屋物原下、道祖の元、鎔物師口上、物師口下等がある。
庭木の鶉手
此地薪料に富み、且原料地なる神六山に近便宜を有してゐる。而して又製技に長しことは發掘せる古窯品を見ても、同系と稱せらるる武内窯と比して敢て遜色なきものの如く中には鶉手などは他山に類作なき優品を遺してる。(白に卵色又は褐色などの土を練り合せて巧みに斑文を現はすものにて、信楽焼の「揉み込み」と同技巧であらう)
土井木原
土井木原の古窯品には、栗色釉に白にて紗綾目文やギリ模様を現はせし緑淵に、見込みには群菊花を白描せし尺口の目積皿があり。白化粧地に四段花模様押文を繞らし、上に青藥を掛けし八寸皿がある。或は薄褐色釉に白と紫にてなだれ刷毛目を飾せる七寸皿など、何れも高臺廣く無釉である。
栗色地にて緑淵には白の波模様、中は白釉にて立筋を引き続らし、それが乾かぬうちに横筋數段を続らして、立筋を掻き跳ねし文様を見せ、其上に金茶を流せし尺三寸の水鉢があり。或は同地に波刷毛目を施せし徳利がある。又赤錆地に飴釉を掛けそれに白琺瑯を流せし尺口の徳利や、青味栗色釉に白にて螺旋筋を繞らせし六寸の徳利等がある。
板屋窯の谷
板屋窯の谷の古窯品には、鐵色地無釉尺口の大胴花瓶や、黒鐵地にトロ色釉涙痕にて、獨樂形肩張四方結び穴附尺五寸の葉茶壺があり、又同鐵地に白化粧掛耳附五寸の花立がある。
板屋物原
板屋物原の古窯品には、鐡地に白化掛の徳利や、同地にトロ色釉を施し、縁邊には白色釉を掛けし尺口大胴張の徳利がある。
芋母口と河内口
芋母口の古窯品には飴色釉に花三島手を飾せし瓢形の小徳利があり。河内口の古窯品は概して甕類や壺及蘭鉢等の大物にて、此處は一名甕屋といはれてゐる。製品の中には鐵地肩附形に押文様を繞らし、それに飴釉を流せし尺五寸の花瓶なども焼かれてゐる。
庭木の古窯品
其他庭木の古窯品中には、小豆色地に白の波刷毛目を施し、底は菊紋刷毛目を文し其上に青藥と金茶を流せし大皿があり。又茶色釉に白の網刷毛目や波刷毛目をせしもの或は剣先三島手の精巧なる大皿がある。そして裏部は縁邊の外全く無釉であるのは庭木皿に共通である。
又暗線釉に篩目や波刷毛目などを六段に文飾せし大皿があり。栗色の薄釉に白の筋を廻はしそれに男波女波の雄勁なる櫛目を掻き其上に青藥をむら流しせる大皿がある。又薄栗釉にて縁には小形立浪刷毛目を施し、底には渦刷毛目をせし大皿がある。
或は暗色鶯釉に白化粧を掛け、緑邊に網櫛目を掻きし大皿や、黄色釉化粧掛に底を波形に櫛掻せし大皿がある。又鶯茶釉に白にて三島手を文し、底には菊文櫛目を施せし大皿があり、或は底部獨樂筋刷毛目の上を、濃茶釉にて總掛したる八つ目積の大皿など何れも高臺部弘く無釉である。
天和年間(1681-1684)有田の坂口權藏なる者來り、此處の庭木燒を平戸地方に運びて大に販賣せしといはれてゐる。
庭木の磁器製作
其後いつ頃なりや不明なるも板屋、河内口の原料を發見し、有田の工人を招きて磁器を製作せしが、何れも軟質にて薄鼠色を呈してゐる、それは土井木原と河内口と二窯の外、今悉く磁器の殘缺が發見さる、此中色相清白に焼かれし分は、晩年神六の石へ天草石を加合せし製品であらう。
板屋磁器
板屋八人塚古窯の磁器の中には、廣緑形耳附五寸の花立に、下呉須にて松竹梅を描きたるが、其筆勢飛んで逸するが如き奇抜さがありそして同柄の油瓶などもあつた。板屋物原の磁器には、染附肩張口附の徳利や大白口反の徳利などがあり。其他の古窯磁器には鳶色又は黄色の食碗及び皿等がある。
而して此木の磁器は、今より百二三十年以前廢窯に帰し、或者は大村領の三の股に、又は有田鄉黒牟田等へ移轉せしといはれてゐる。此地韓人の墳墓とせしもの道祖の元に二十基許りの土饅頭ありしも、いつの頃か畑地に墾かれて今は其影だにない。
土井木原の古窯
當時の古窯として残れるは土井木原のみにて、七八室の間敷の中に大なるは五六坪の廣さがある。此處の百姓にて仕事嫌ひの靑年などが、折々行方が知れぬとき此古窯を探索すれば、大方此内に晝寝をしてるので、此古窯をけ者の隠れ家と呼ばれてゐる。
梅の木原の韓人屋敷
又梅の木原には高麗人の住宅とて、草葺屋根の長さ十間入り六間、それに玄關が突出され前には立派な庭園があつだ。然るに颱風にて全く崩壊されたとのことである。想ふに韓人の一世帯が住宅と工場とを兼ねし建物なりしが如く、今此家にありし一臺の陶車が遺つてゐる。
百間窯と庭木
此地韓人の開窯後、何れの陶山より多くの工人が任せしかは不詳なるも、現今住民中に住吉村立野川内なる悉地院の檀徒が十八戸ある。此處立野川内とは二里半位隔てゐるも、そこが百間窯の所在地なることを考察するときに、或は其百間窯の流れ人が庭木へ轉任せしにあらざるかを思はしむ。而して此地今や農村と化し終り、小學校内に若干の殘缺を見るの外陶煙全絶えてゐるのである。
小田志山
此處の飛松峠を越ゆれば小田志山である。此地又全く頽廢に儲し全村戸數百二十戶の内、陶山の村落は僅に三十戸に満たず、中に窯焼は唯一戸のみ残つてゐる。此處の古窯趾は大川口新窯の外新立山、小田志窯の頭、白木原、上松山、下松山、野仙谷、樫の木山、瓶屋谷一の窯、同二の窯、同三の窯等である。
新立山
新立山の古窯品には、大綠鉢に七段筋を廻し、其問へ花形押文を繞らせる上に、白の化粧掛を施せしが、地質炻器の如く硬度に焼かれてゐる。そして高臺裏弘く無釉なると作風とに於いて、概して小田志は庭木と相似たものである。
小田志の窯の頭
窯の頭の古窯品には、薄栗色釉の上に天目吹掛の茶碗があり又栗天目の大皿に印花式にて櫻花紋及菊花紋を繞らしたのがある。
或は灰色釉に白にて三本の獨樂筋を廻はし、それに青藥を流せし大皿や、暗色灰釉に白の獨樂筋を廻はせし大皿などがある。
白木原
白木原の古窯品には、栗色釉に波刷毛目を施し、見込みの上を目積せし縁反尺口の皿がある。
樫木山
樫の木山の古窯品には、栗色釉に白釉の飛化粧を施せる目積大皿や、栗色薄釉に四段筋を廻はし、其間へ三島手文様や印花文様を繞らせ大皿がある。或は薄紫釉に段筋彫の合間には唐花及剣先三島などの押形飾を繞らせし八つ目積の大皿があり。又天目釉白刷毛目文飾の徳利や黄瀬戸釉に緑天目を掛け、胴には粗笨なる菊を鐵描せし徳利などがある。
ヒウラク山
此にはヒウラク舞と稱する巖山がある、それは當時の韓人が此山上に押連れて酒宴を張り、そしてヒウラク舞を踊りて望郷の念を散しところにて、彼椎の峯の山登りや武内のヒウラク舞と同一であらう。
小田志磁器の創始
小田志の磁器の創始はいつ頃なりしや確かならず、或は享保年間神六山及び頭先の谷より磁石を見せしよりこの説あるも詳でない。蓋し最初發見當時に於いては、くろ物の化粧掛や刷毛目などに用ひ居りしを、有田の磁器製法が習得されてより、愛に始めて軟質の磁器創製し得ものであらう。
此地方へも天草石の使用傅播され、之に神六等の地土を加合して盛んに食器類を製したのである。然るに文政十一年八月九日(1930年)の大暴風は、此處の陶業にも大なる打撃を興へたのであつた。
樋口親治
此脅威の爲めに小田志焼の衰滅せんことを憂ひたる樋口親治は、大いに之が挽回策に腐心した。
然るに此暴風の夜の大火にて、焼出されたる有田皿山の職工は陸績として入來り、此處に移住する者百餘人を算せらるゝに至つた。之より小田志製品の面目を一新すると同時に、有田焼の休業に 困りて其代品供給の利を収めたのである。(此當時有田の馬場伊兵衛其他が此地へ古陶車を所望に來しといはれてゐる)
小田志製品の向上
製品向上の一例は、従来の茶漬茶碗には皆胴のみの散畫なりしが、此時より有田式に腰描き又は縁描きを加へ、内にも底繪を文する高級品が出来、又細工の如きも頗る巧妙さなりしかば、之より此地方にては小田志物として格段の價を生するに至つたのである。斯くて親治は翌十二年五月大川口に新窯を増加築造し、鋭意改良の道を講しより、彼は宗藩鍋島家の御用品製作を命ぜらるゝに至つた。
松尾喜三郎
明治年間に至り松尾喜三郎(善左工門の子)ありて、大いに斯業の開發に努力し功績顕著にして、小田志陶業中興の觀があつた。彼は又意匠圖案及釉薬調製其他の窯技に於いて、抜群の技能を有せる名陶家であつた。明治十八年六月東京上野に於ける商絲、織物、陶漆器共進會開設の際、時の農商務大臣西郷従道は、初代柿右工門等と共に、喜三郎へ功労賞狀並に金參拾を添へて授したのである。
浴槽用タイル
明治二十二年喜三郎は、風呂槽用六角形組合せの染附タイルを創製し、當時の内國博覧會に出品せんとせしが期を逸して果さず、之が後に嬉野温泉場の特等浴槽に使用されしものである。又銅版轉寫の如きも、喜三郎が率先して此地に普及せしめしものにて、斯くて大正四年八月四日八十二才を以て卒去したのである。
樋口治實
明治二十年十二月二日此地の樋口治實(治孝の男棣花堂)は、含珠焼を發明して第四○五號の専賣特許を得たのである。彼は甞て磁器の破片中に偶々透明物あるを發見し、之が素質中には必ず燦然たる透明の紋様を顯はし得べき方法ある可きを考察し、爾来刻苦惨憺たる研究を続け一時は家産を蕩壺して沈淪の極に陥りしも百折撓ます、明治十九年に至つて漸く完成することを得るに至ったのである。
含珠焼
それは或部分には染附ありて、其一面に散花の如き文様を素地に現はしたるものにて、明の螢手よりも精巧なりさ稱せられた。そして同二十二年二月憲法發布の記念として、菊桐の御紋章を透明に顕はしたる御湯呑を謹製し、之を宮内省に献上して同省の御用を命ぜられたのである。
(含珠燒は毀損多く生せし爲せざりしものの如し)
棣華會社
之より先同二十一年十月治實は、資本金一萬圓を募集し長崎本興善町七番地に於いて棣華會社なる海外直輸の貿易商社を組織する等、種々の事業を經營せしが、昭和五年七十九才にて卒去したのである。(明治二十九年上波佐見山の田中宇太郎又含珠燒を製作し、大正十三年頃止みし稱せる)
前記の如く此地韓人の創業以來製陶頗る優技を示し、磁器時代に於いても亦小田志物さて此地方陶山の首位にありしが、今や全く廢滅し、現在にては斯業の家奥川龜右工門のみ一人石炭窯にて食碗を製造し、弓野人形の外南部杵島の皿山に名残の陶煙を繋げてゐる。
藤津莊
藤津はもと國栖津又は葛津と稱し、往古は土蜘蛛人種の住みたるところと稱し、肥前の國中最も古くより民族の棲息せし土地といはれてゐる。人皇十三代成務天皇の五年九月國郡に造長を立てらるゝに至り、椎彥命葛津の國造に任せられ、其子孫代々五丁田より此地方を支配しが、後裔精武城(杵島郡龍王村)主藤津藤太郎に至りて杵島堺より鹿島の一部を領有するに至った。
正曆五年(995年)藤津の莊は大村の領主大村直澄の支配地と成った。
伊佐兼元
寛仁三年三月二十七日(1020年)刀伊の賊我が松浦の沿岸を侵すや、此地の郷士伊佐平次兼元(真言新義派開祖興教大師の父)上松浦の大川野三郎知と共に戦功ありて、太宰府の府官となり莊園四ヶ所を領有し、大村氏に属し藤津の地頭職となった。
降って元寇の役に於いて、大村氏の支族大村又太郎家信、其子平太郎家直は、大草野の彼杵氏、塩田の原氏と共に戰功あり、家信は能古見の城主として藤津の一部を領有し、嬉野氏の昶白石氏叉其一部を併有した。
文明元年(1469年)蟻尾城主大村家親は、千葉敷胤を破って自領藤津の外杵島を併有した。同九年千葉胤朝攻め來つて藤津を侵し、蟻尾城を陥れて勢威大いに振ふに至つた。
有馬氏の勢威
明應三年(1495年)大村氏の系高の有馬貴純下松浦を征服し、功に依つて藤津全部と杵島の内白石、長島の兩莊を併領した。其孫晴純(仙巖)に至り將軍足利義晴の相伴衆となり、高來、藤津及杵島の一部にて三十一萬石を知行し武威近郷をし、之より小城方面に侵入して佐嘉の龍造寺隆信と覇を争ふに至つたのである。
天正四年(1577年)有馬義直(晴純の男)は鹿島の鷲巣城を本營さし、其子義純は濱の松岡城に屯し、鹿島の構造城(一名横澤城)には深町尾張守、原左近太夫氏長 能古見城主)、岩永和泉守等をして守らしめ、又五丁田の鳥附城を固め、其他藤津の豪族鹽田籾岳の城主原豊後守尚家、嬉野鷹野の城主嬉野越後守通盆、同岩谷の城主嬉野大和守通春、同日守の城主嬉野淡路守通吉、吉田の城主吉田左工門太夫家宗、久間の城主久間權郎盛種を始めとして、高來深江の城主安富下野守純泰、同田比良の城主田比良左工門、同小部の城主小部右工門佐、其他上流、伊福の諸將等ひしひしと堅守したのである。
隆信有馬軍を破る
同年二月六日龍造寺隆信は杵島の須古城を根城として藤津の有馬軍を進撃し先づ横造城を陥れ深町尾張守、岩永和泉守等を田備前守純晴、吉田、久間及嬉野一統の諸將を降討取り、そして原越後守家盛(尚家の長子倫行)永し、森の岡に一砦を構へて犬塚弾正少弼鎮家(蒲田城主後龍造寺播摩守盛家)、徳島筑後守胤時を置き、恒廣には鍋島豊前守信房(直茂の兄)を備へしめた。又鷲巣の城には嬉野陸奥守通時、松岡城には横岳兵庫頭家實、上瀧志摩守盛貞、永田右京亮通清、徳島左馬介信安(芦刈城主)辻甚九郎等をして攻略せし諸砦を各藩代りに守らしむるや有馬軍は退きて再軍備を固めつゝあつた。
伊佐早と大村を降す
天正五年隆信は鍋島飛彈守信生(直茂の前名)、小川武藏守信俊(直茂の含弟)、納富越中守信安を先鉾として、伊佐早の西鄉刑部太輔純堯、深堀の深堀中務少輔純賢、貝津の貝津豊前守、矢上の矢守伯耆守、江の浦の江浦左衛門、長濱の長濱藏人等を攻め降し、大村丹後守純忠又純堯に依って和を乞ひ、そして女を隆信の次子家種に配はすに至った。
高來を攻略す
之より隆信は高來に進撃し神代俵表の城主神代兵部太夫貴茂、長田左京、深江の城主安富下野守純泰、島原の城主島原式部大輔純豊 安徳の城主安德上野介純俊(入道惟山)等皆戰ひ利あらずして龍造寺軍に降り、有馬鎮純(義直の子)遂に屈して媾和するに及び、兄義純の女を隆信の長子鎮賢(後の政家)の室と成すに至つた。
之より戰亂漸く治まり、藤津の各邑主はそれぞ自己の采邑に安堵し、龍造寺氏の配下として治政且其産業に努むるに至った。其後天正十二年(1585)隆信再び有馬を攻めしが島津氏の援兵と戦うて利あらす、三月二十四日島原に於いて戦死し、同十五年(1588)其子政家肥前七郡に封ぜられしも、後年鍋島直茂之を襲ぐに至り、次子和泉守忠茂へ二萬石を分興することゝなった。
忠茂封土
翌十六年十一月(1589年)忠茂は下總國矢作より、此地藤津郡鹿島へ移封したのである。鹿島鍋島系圖左の如くである。
(鹿島鍋島系圖参照)
而して藩制時代の藤津は全く分割され、鹿島、濱、能古見、古枝が鹿島藩の領地であり。鹽田、久間、五丁田、嬉野及び吉田の一部が蓮池藩に屬し、勝茂の三男甲斐守直澄の領地であつた。又七浦と吉田の一部と嬉野不動山の皿屋谷、内野山及志田東山だけが宗藩佐嘉の支配地であり。多良と大浦は龍造寺の系諫早氏の領地であつた。
嬉野焼と不動山
抑嬉野焼の創業は、後花園天皇の永享十二年(1440年)平戸より上陸せし唐人(韓人なるべし)藤津の莊不動山に來りて陶器を作り、同時に又自家用として茶樹を植えつけしものが、嬉野焼と嬉野茶の創始であるといはれてゐる。永正年間(1504-1521)明人紅民なる者南京釜(唐釜)を持て茶業を創始した。其後陶業打絶えしを弘治年間(1555-1558)復興せしものである。
不動山の切支丹扶植
當時宇禮志野但馬守通久の代にて、其頃壓迫されし大村領なる切支丹の宗徒は、山脈傳ひに不動山へ潜入し、永祿(1558-1570)の頃まで十五六年間此地に潜伏して斯教を扶植するの深きものがあつた。其頃陶業衰に歸せしを、慶長の朝鮮役後韓人此處につて再興せし傅へらるも、それが内野山を復興せし相源の仲間なりや、或は又他の韓人なりしや詳でない。
切支丹の厳禁
慶長五年(1601年)鍋島勝茂の許を得て、鹿島、武雄等に耶蘇寺を建立せしことあり、此時不動山も公許となりて一時信徒の隆盛を極めしも、同十九年禁制を厳命さるゝに及び、寛永十年大村四郎兵衛の如きは唐津に遁走せしを逮捕の上刑死されし者にて、此處は切支丹教徒の潜伏地としても有名であつた。
嬉野茶の始
之より先慶長八年(1606年)杵島郡白石南郷の大庄屋吉村新兵衛氏忠(今の卯太郎八代の祖)は不動山に来り、製陶地の副業として皿屋谷の山谷を開墾し、茶樹の栽培を行ひしより、全村智之に倣うて茶業彌盛んなるに至つたのである。そして氏忠は明暦三年三月廿四日勝茂の卒去を追って共年の四月十一日殉職したのである。其後製茶の方主業となりて陶業漸々と衰退し、途には全山茶樹の栽培地と化し、皿屋谷を改めて新屋谷稱したのである。嘉永六年長崎油屋町の大浦慶女が、同地出島の蘭入テキストルに諮詢して嬉野茶の見本を提供せしより、英商ウオールドの注文となり、近來露西亜向として大に歓迎さるゝに至り、嬉野茶の年額十萬圓を暴くるに至った。
元來不動山は蓮池藩の採邑なるも、皿屋谷のみは本藩の支配地であつた。現今上不動山丈にて戸数百二十戸、內皿屋谷が三十五六戸ある。嬉野より彼杵街道を右手へ二里の登りにて、大村領波佐見陶山へは不動山より一里の山越しである。今や陶業全く絶滅せるも茶業は年々に達し、上不動山のみにて年産額一萬圓餘の製出と稱させらる。而して茶樹の栽培地質と陶土を産出する地質とは、そこに一脈の關係があるらしい。
皿屋谷の窯の谷
古窯趾としては皿屋谷の窯の谷最古く、次は下皿屋谷窯、管田(一名枯木)及大船等がある。窯の谷の古窯品には粗土にて製せる無釉陶器がありて、糸切底の堅く燒締たる四五すの淺茶碗より六七寸の淺井などがあり、それは恰も先住民族の遺物らしき元始的製品である。
又此處の舊家吉村卯太郎の所有品にて、褐色胎土に鶯釉を掛けし七寸程の水指(蓋なく口邊破損しており)ありて、それが胴を螺旋形に荒削りせし刀痕を見せ、尚糸切の底部まで施釉せるが古色蒼然たるものである。又此處へ隣山三の股の磁石を越えに運びて用ひしものゝ如く、薄鼠色の種々の雑器を焼てゐる。
或は稍白き磁器にて海鼠葉形の手塩皿があり、青磁物を焼いてゐるが、それは或時代の韓人が此手の製作を得意とし、隣山大村領の陶山へ其製法を傳へし稱せらる。そして今軟質らしき薄青磁や天龍寺手などの殘缺が轉がつてゐる。中に天龍寺靑磁にて外面に剣先繞らしの浮彫を施せし六寸丼など全く李朝式を摸せしものにて、之と薄砧地袴腰の盃臺などは天草原料を以て製せしものの如く、そして又天草石にて種々の白磁が焼かれてゐる。
管田
管田窯は前記の場所より一丁斗り下りし向ひの山裾にて、皿屋谷下窯と流れを隔てゝ向き合に成つてゐる。此處も最初は黒手物を焼きしと見へ、稀に灰色釉高臺無釉の茶碗や飴釉の同手の小皿などが發掘さる。降つて明治二十年頃(1888年)彼杵の丹生末吉が此地に来り、木原山の石丸鹿吉及鹿太郎父子を頭梁として、三の股の窯原料にて磁器製造を起せし由なるが、蓋し専ら天草石を主料とせし如くである。斯くて經營難に陥り幾許もなく廢窯せしものであらう。
此處の古窯磁器には、縦筋の中へ四方捻形模様の染附小皿や、又同じ筋内へ浪繪を描きし同物があり、或は同染附の五六寸皿がある。就中五六寸丼の龍畫の如きは、宛然支那の古染附に見る奇抜な書き振りである。なほ下皿屋谷窯の殘缺も、此嘘と大同小異であるらしい。
大船
皿屋谷の下隣なる大船村落に於いて、明治の初年(1868年)同地の山口民三が製陶業を起し、天草原料に三の股土を加へて盛んに染附物の食器を製せしも、此處も亦全く廢窯に歸してゐる。現今不動山の古窯趾として、以上四ヶ處を數ふるも、當時を推考すれば皿屋谷より此大船地域までには、尚幾許かの陶窯ありしにあらざるかを想はしむるのである。
或書の嬉野焼といへるには、享保年間、弓野の淵孫左工門、其子七右工門父子陶工として名あり、又瓦を焼く。次に溝口市兵衛、高町藤兵衛等磁器を製せんとするに當り、従前の陶窯にて焼かんせしも(酸化焰にて焼きしものならん)途に成らず。文化頃西田市兵衛巨財を投じて嬉野燒復興に努力せしも途に振はす等々の記事がある。
西田市兵衛の下宿焼
西田市兵衛は嬉野下宿(戸數五十戸)の舊家市郎右工門の男にて、當時下宿焼と稱させられしもの、實は此地にて製造し物にてはなく、此處の管谷といへる谷山より粘土を採掘し、そして小田志山に運びて黒物を製せしものにて。今同家にある尺五寸の大徳利を見るに、赤き胎土に飴釉を施し、肩部と腰に三島手を印花せるが、中胴には白にて小さき鶴と鷺を象嵌し、嘴と脛を鐵描せしものである。斯くて市兵衛は文政十二年十月十一日(1830年)卒去してゐる。
鷹の巣甕山
同下宿大字鷹の巣の稲荷山に於て明治二十二年春此地の小野原清吉が、六間登を築窯して甕類を焼きしものが甕山である。原料は此處の地土を用ひ、甕の外土管、擂鉢、蘭鉢等を製造し、年額三千圓を塞げたりしが、大正五年其子雪松の代に於いて廢窯せしものである。
内野山高麗神
嬉野内野山の、新窯と下窯との間なる松樹の下に、天神祠と並び建つ高麗神の石祠には、天正十六年(1589年)の彫字がある。それは屋根造りにて観音開扉の中に、神像が高浮彫に現はされてあり。 なほ傍に明和九辰三月吉日(1772年)山中と刻まれてある。
明和九年は、此地悪疫流行して全山に蔓延せしかば、内野山の山中より其祈願して彫込みしものらしく、元此石祠は別地高見といへる處に祀りありしを、昭和五年天神祠と並べて此處に移轉されしものである。而して此處の殘缺を檢するに、天正時代の開窯とは認め難しさの説あるも、慶長と天正とは五六年の隔りである。而して此物原調査とても、徹底的の検討なりや否やじ難く、故に此認めざる説を認めざる説もある。精しくはなほ調ぶ可きであらう。
相源と金源
慶長三年鍋島直茂朝鮮役より歸陣の頃、我邦に渡來せる韓人の陶工にて、相源、金源及外一名の者此内野山に来つて旅装を解きしといはれてゐる。而して今此處には相源の墓碑のみあるは、他の二人は此地を去って他山に開窯せしにあらざるか詳でない。
相源の大墓碑
此處の高尾山腹の墓地に、高さ八尺、巾二尺一寸の平面なる大墓碑とがあり、表銘には清譽妙讀と心月妙績とが並記され、右に寛永十七庚辰八月十三日(1641年)として下に相原宗左工門尉とあるは其子であらう、之が相源夫婦の墓碑である。
今其後裔相原作といへる者、此地に農業を営んでゐる。そして内野山の窯焼は例年二月十五日十一月十五日の両日、此相源の碑に祭典を執行することが慣例と成つてゐる。猶此墓地には自然石に完月妙真と刻せし韓人墓らしきものがあり、それに施主人か小島伊衛門と記し、右に延寶甲寅二年にて(1645年)と刻まれてあるも、果して然るや否や詳でない。
内野山新窯
内野山の古窯趾は古窯と下窯及新窯の三ヶ所である。新窯の古窯品には、外靑地に内は青釉を掛けし窯變の茶碗があり、同じ窯機にて蛇の目積の中皿や、灰色釉底三つ目積の茶碗がある。又同釉にて突蛇の目積五寸の丼や外鼠色内空色釉なる茶碗があり、或は暗黄色釉の半磁器茶碗など、何れも高臺無釉に焼かれてゐる。
内野山下窯
下窯の古窯品には、外黒釉に内は白の琺瑯流しにて、蛇の目積七寸の淺井や、内白琺瑯にて外黒釉なる蛇の目積六寸の丼があり。又鶯釉八寸の淺井等何れも高臺無釉である。或は栗黒釉に白釉の波刷毛目を施せし蛇の目積八寸の丼などもある。
其他此處の古窯品には、口黒にて胴鐡色釉に白釉流しの徳利や鶯色釉に口遊天目の徳利がある。古窯の殘缺を見るに、前記二窯の破片と異なるところなきは、察するに此處は古き廢窯趾とて、此物原へ前二窯の殘缺を運びて打来てしものであらう。又此内野山製品には鐵暗色なる六寸の目積皿が當時肥後行きて多く焼かれてゐたのである。
之より先寛永年間(1624-1645)に至り、其後渡來せし韓人の子孫と、内地人との斯業者大に繁殖し、又地方よりの轉住者も増加して戸數百七八十戸を數ふるに及び正徳の晩年(1716年)より、従来の陶器の外、天草石を主料として更に白磁を製造する者生じ、古窯の外に下窯及新窯を築造するに至つたのである。
内野山番所と保護
内野山は鍋島宗藩の支配地とて、製陶の保護又頗る厚く、此處の陶山を貫通す南北の出入口には閲門を設けて番所を建て、見張役の傍には槍、棒、袖搦等を備へて警固され、張りに旅人の通行を禁じられたのである。
寛保年間(1741-1744)より有田代官の所轄に属し、毎年正月には當山より精製せし高麗焼の酒盃と、床置物を宗藩主へ献納する事が定例されてあつた。又有田の横目役所(元の代官所)に於ける年始の蔵盃と、銚子の製作も此内野山焼のくろ物と定められ、毎年末に此處より納められてゐたのである。
又此地に費消する製陶燃料は、二十四個處の地元山林より、僅少の課金を以て下附されたのであつた。そして例年六月二十日限り返納すべき規定を以て、有田代官の手を経て、窯焼資金なるものを貸興されしが、それは全山に玄米百俵と、金子三百両に限られたのである。
疫病後の頽廢
然るところ明和の末年に於いて此地の疫病激甚を極める者算なく、其上凶年打績きて米穀不作の爲め、営業者は全く疲弊の極に達し、本藩より救恤を喋りしも、此頃より數百戸内外に減じ、古窯と下窯は遂に廃窯さるに至つたのである。
其後維新當時に於いて、なほ十六戸の窯焼を有せしも漸時衰頽し、爾後十四年を経て新窯は火災に罹りしまゝ再興せず、倒産する者他業に轉する者相次ぎ、残りしは磁器焼にて三戸、陶器燒にて一戸となり、職工又僅に十四五人に過ぎさるに至つた。
富永源六
明治二十一年(1889)此地の富永源六は一の新窯を築造し、青花の磁器を製して頗る名声を揚ぐるに至りしが、同三拾年には残れる四戸の窯焼中三戸は廢業して源六一人の内野山となり、往年彼の高原五郎七にまで訪はれし此地の高麗燒も、途に其跡を断つに至つたのである。
源六焼
之より源六は全國各地の製陶を観察して具さに研究せる結果、茲に一種のオリジナリテイーに、源六焼なる作風を製作した。それは染附墨きにて牡丹を書き、花を正圓子にて彩色し葉を呉洲にて隈取誼染せしものである。そしてマークには(トミの意)の銘が用ひられ、同四十四年には源六燒株式會社を設立して、嬉野温泉に添へろ一名産と稱せらるゝに至つたのである。
新湯温泉のタイル
今嬉野温泉の新湯には、源六製染附の六角と、四角のタイルが使用されてゐる。其底部用のタイルには、浴客の滑りを防ぐため、象や龜などを浮彫されてあるが、彩料には呉須の外金茶や緑及正圓子等を用ひ、竹の子、佛子柑等種々の畫り式にて、蓮池の永田石梁(成富椿屋門人明治二十八年卒、五十九才)が書きしものである。
富永源六は大正九年二月五日六十三才にて卒去した。彼は明治二十二年西嬉野村長となり同三十二年には佐賀縣々合議員に擧げられたのである。
二代源六
長子真一(有田工業學校第二回卒業)二代源六を襲名し、大正十一年一月源六燒合名會社に改めたのである。 二代源六は、大正十二年七月四日第五〇四三號陶磁器焼成用連結窯につき特許を得たのである。
海江田侍從御差遣
同十五年肥筑平野に於ける大演習舉行の際、總帥閑院宮載仁親王殿下には、産業御奨の思召を以て、特に海江田侍従を源六燒工場へ御差遣遊ばされたのである。
昭和四年十月には、又源六燒株式會社の組織に変更し、今や別府市流川通、佐世保市島瀬町、佐賀市呉服町等に支店を設け或は長崎市鍛冶屋町に代理店を置き又嬉野町には源六燒事務所がある。
吉田山
藤津郡吉田の開地は頗古く、此處の村社章筒神社の勸請に、和銅二年九月三日(710年)とあるを見れば、人皇四十三代元明天皇の御代既に此集落ありしことが察せらる。降つて後白河天皇の明應年間(1492-1501)某太郎左工門尉なる者吉田鄉三百拾町を領し吉田を以て姓氏さした。
吉田家宗
それより數代の孫左工門太夫家宗に至り、高來の有馬氏の旗下たりしが、天正四年二月(1577)龍造寺隆信攻略し來り、對戰利あらず、家宗は嬉野諸將と共に隆信に降ったのである。同年 六月隆信は大擧して高來の有馬領へ進軍するや、家宗は手勢を率ゐて東道の役を命られたのである。
鳴川石の發見
此時彼は吉田莊内なる閑道を過ぎる可鳴川に差かゝるや、川底に安山岩の白石あるを発見し、直に馬を止めて之を探らしめしが之が吉田石の採掘されし動機である。此兵馬惚の中に於いて、治國興業の念深き家宗が人さなりを察す可きであらう。
鳴川石の分析表(吉田鳴川石の分析表)
珪酸七六.三七% 礬土一三.八九% 酸化鐵〇.六二% 石灰〇.四四% 苦土〇.〇九% 加里四.七九% 曹達三.三八% 灼熱減量〇.六八%
吉田皿屋
蓋し當時は隣地の陶山より此原料を探して、陶器の化粧掛や刷毛目などに使用せしものゝ如く、後年有田磁器の製法傳へられてより中通なる鳥居原の礬土(含水珪酸礬土なるべし)を加へ、此地に於いて薄鼠色の軟質磁器を焼くに至り、陶家又漸時増加して十二戸を数えるに至り、此處を吉田皿屋と稱するに至つた。蓋し中通一名藤津系 嬉野窯上吉田の地である。
傳兵衛領地
鍋島勝茂が父直茂の封を襲くや、吉田は伯父豊前守信房の采邑となり、慶長十四年(1610年)に至つて両岩は鹿島領へ分割し寛永十六年(1640年)吉田の地は蓮池藩の領地となった。そして吉田の内納戸料、中通寺邊田、峯の村、萬財、岩の下、赤瀬、川内、春日を信房の孫傳兵衛茂(實は武雄の後藤家信の次男也、伊萬里系圖参照)の領邑として、二千六百六十石を知行せしむるに至つた。
此吉田の半地なる傳兵衛領邑だけは、本藩の支配に属するを以て、此地の窯焼へは特に賓暦十二年(1762年)より、有田泉山の磁石五百苞(四萬二千五百斤)だけ毎年採ることを赦されて、明治十四年頃(1882年)まで此皿屋に於いて製陶せしものである。然るに其後隣地なる蓮池領吉田山の勃興に依りて此地の窯焼は悉く之に移転するに至り舊吉田は全く廢窯に帰したのである。
今の吉田山
現今の吉田山と稱するは、蓮池藩の領地にて、最初は皿屋と同じく鳴川石を主料として製作せしものであつた。此處の古窯品とて發掘せる小皿や茶碗を見るに、何れも鐵分多き色相を呈し、之に粗笨な吳洲畫を描きし軟質磁器である。此地の創業は詳ならぬも、前記皿屋人の轉住と、内野山陶家の移住ならんさ推せらる。蓋し吉田山發展の基礎を造りたるは、蓮池藩祖直澄が大いに斯業を獎勵せしに因ることは勿論にて、蓮池鍋島系圖左の如くである。(蓮池鍋島系圖参照)
鍋島直澄
鍋島勝茂の三男にて、寛永十五年二月二十七日(1638年)島原切支丹の敵城へ一番に乗込んで、勇名を天下に馳せし甲斐守直澄は、本領神埼郡蓮池に於いて五萬二千六百二十五石を、嗣子攝津守直之に譲り、同十六年八月二十三日別領地藤津郡内(二千六百二十五石)五丁田に退隠し、専ら産業獎勵を志し、采邑地の陶業を補助したのである。
南川原より指導者招聘
直澄は始め五丁田に於いて斯業を試みしも、此地製陶に適せすさなし、先づ吉田の陶山を發展せしむべく、領地なりし有田郷の南川原より、副島、牟田、金ヶ江、家永の四人を招致して指導者となし、従来の小窯を廢して大窯に改築し、其製造と販賣に便宜を奥へし而已ならす、窯焼には物資を補給するの外、門地を尊ばしむる等、あらゆる優遇の道を講したのである。そして五丁田の陶業は承應年間(1652-1655)之を久間村に移轉せしめたのである。蓋し久間村の開窯は明暦年間と稱せらる>も實は既に此時創始されたものであらう。
五丁田の窯の口
直澄が五丁田に於いて開窯せ場所は、今何れなるかは不明なるも、此地には火の口、又は窯の口なる地名あるに鑑みて物色せしに、窯の口と稱する處は直澄の吉浦別邸趾と、五丁田小學校との間にある馬蹄形の杉谷にて、一見せし丈けにては當時の残屑を見出し得ざりしも尚一歩を進めて探究すべきであらう。
吉田窯焼數の限定
斯くて直澄は、吉田の高地に醫福寺(明治八年炎上し、其跡へ今大定寺が建立されてゐる)を開基して別隠居所となし、従来の窯焼へ連れりし蓮池藩士と、それに副島等四人の指導者を加へ、総計十六人に限定して陶業を經營せしめ、已れは醫福寺の高所より、其陶煙の擧がるを望みつゝ親しく斯業の扶掖に力めたのである。
此十六人の窯焼には、斯業保護の爲め永代許可の特権を興へ、後之を十七人半と定めて、直澄自ら其一人半前の権利を保持しが、卒去するに及んで此内の一人前は消滅に歸せしめ、半人前を副島茂右工門に増興して、爰に十六人半と改めらるゝに至つた。但し此割當は登窯の間数と、大小に依って割合はされたのであらう。
副島茂右エ門
此初代副島茂右工門は、南川原より來りし指導者頭にて、特に直澄の知遇を得し者らしく、そして彼は正徳四年六月十九日九十六才の高齢を以て卒去した。斯くて吉田及久間山の製陶を育みし領主直澄は、寛文九年三月五日(1670)行年五十五才を以て五丁田村なる吉浦の館に卒去したのである。
村雲の鴉
直澄は卒去したれども、吉田山窯焼の権利保有待遇には、永代易らざるべく保護された直澄の墨附があり、之を叢雲の鴉と稱し此處の斯業者には無上の賓卷であつた。此掟の中には吉田山中にて呉服屋、酒屋、米屋或は豆腐屋に至るまでの商賣は、皆窯焼の営業權内に附属せしめあるを以て、是等の商人は窯焼組合の許可を得されば、営業し能はざるのみでなく、此の總ての営業運上は窯焼が取立て、之を勝手に使用し得權利さへ附興されてあつた。
窯焼の兼業權
蓋し此の諸營業は、最初より窯燒保護のため、其兼業として興へられしものにて此十六人の斯業者中にて、米屋も、酒屋も、呉服屋も、持廻りに營業することゝ成つてゐた。故に此組合の下に營業を許されし商人は、少しく窯焼の反感を買ふことあれば、彼等は不當なる多額の納税を課せらるゝ故に、岡三平の如きは此煩に堪へず、後年多額の一時金を出して、酒造權を組合より買収せしといはれてゐる。
吉田下窯築造
其後斯業の發展と共に、十六人の窯焼の次男以下營業用の名義を以て、藩の許可を得ることゝなり、資本家副島彌左工門が、新たに下窯を築造せしは、文化年間(1804-1818)であった。而して窯焼は少しく資金を要する場合にも、永代潰す可からすてふ、藩祖が奥へし村雲の鴉の一巻を楯にとり、いつも藩主へ出資を過まるのが定であった。之には蓮池藩に於いてもほとほと困却したのは無理もなかつた。
いつの時代なりしか、和田菜といへる代官ありて、此墨附を鳥渡と借受けて、蓮池へ持去りし儘任せざりしかば、藩祖以来の特権保護書も、其名の村雲の鴉の消へし如く、全く雲隠れと成り終つた。蓋し此地の窯焼は明治七八年頃までは、相當に勝手を振舞ひしといはれてゐる。
吉田の茶漬製造
正徳年間(1711-1716)より天草石の使用發見となり、此製陶主料は此處より二里を隔つる田津まで帆船着荷の便があり、之に鳴川の地石を加合して製造すること成った。其重なる種類は廣東茶漬碗や、平茶漬碗にて、全くの日用品であつた。文化文政時代より、窯焼は大阪へ直接取引を開始して、空前の盛況を呈し、斯くて製品の不足を補ふため、従来の前窯及下窯の外に、新窯が築造されたのである。
文政天保の吉田悲境
文政の末年(1830)より、天保の初年(1831)に至り生産過剰を来たし、爲に價格低落して經營困難となるや、さしも往時より豪華な生活を続けし窯焼も、漸時悲境に沈淪するに至り、廢業者相継いで生じ、風雨に晒さる陶窯は雑草生へ伸びて、秋風に戰く惨状を呈するに至つた。邃に窯燒は資金の枯渇を訴へて、其挽回策を請ふに及び、蓮池藩主雲叟(摂津守直興)は、尾形惟晴を遣はして陶窯を改築し、或は物資を供して舊態にさしめたのである。
副島雲月
天保年間(1831-1845)の名陶家副島茂右工門(六代か)は、當時の名君雲叟より雲月の號を授かりし者にて、青花の優秀なる磁器を製作して盛名があつた。彼は又四時庵と號して俳諧を好みしが、當時諸國の俳友より贈られし選句多く残されてある。曾て都の高橋道八(三代)も亦此邸を訪れし一人にて、其製品を残してゐる。蓋し彼が有田に來りし明治の初年であらう。
副島次作
副島家は、代々茂右工門を襲名し者多く、且屢名工が輩出した。八代次作(壽梅茂右工門の養子)の如きも、捻り細工に、彫刻に、抜群の名工なりしが、明治二十六年十一月十四日六十一才にて卒去した。斯くて現代茂八に及んで廃業したのである。
家永家も、後代に至つて廢業せしもの如く(今の教育家家永利三郎、陸軍少將家永直太郎兄弟は後裔である)而して藩制時代の十六人窯焼の子孫にて、今向斯業を経續しつゝある者は、副島辰三郎一人といはれてゐる。
精盛社と副島利三郎
明治維新となり、士族に舊祿公債証書を下附せらるゝや、政府は之を産業に投資して、實業に従事すべく獎勵せしかば、吉田山は副島利三郎(茂右工門の分系)の發案に基づき、地方舊士族の出資を中心として、明治十三年精盛社を設立した。此當時より非常なる好景氣を呈し、同十五年には舊藩の羈絆を脱して、新たに一登りを築窯し、之を社の窯としてゐた。之より以後従来の共同積せし、三ヶ所の登窯は全く痩せられ、後年には銘々個人の登窯が新築されたのである。
而して如上の活況も暫時にして止み、彼の不換紙幣の影響を蒙れる一般の不況は、陶業者のみ獨り逆行すべくもあらず、明治十五六年の難航路に遭遇せる吉田山は、此巨濤を乗り越すべく羅針のコースを更し、従来の内地向製品を、支那向製品に轉換することなったのである。
吉田の支那向時代
此時少額ながら、支那人へ吉田焼の賣込を開始せしは、岩永彌九郎にて、次に将来に着眼して、大規模の取引製造を契約せしは副島利三郎であつた。此好端緒を得しは、恰も爲替相場の下落より貿易の増進をせし如く、當時不況に面して、吉田焼価格の低下されをりし爲であつた。
爾來十數年支那向製造時代として活躍し、非常なる好況をせしより、大串寅次郎、石井種五郎山口又七等盛んに製造した。然るに日清戦争後支那の商人は、長崎よりも神戸の方、自國との輸出入に便利なりしとて、移轉する者多くなり、従つ長崎との取引疎隔すると同時に、従来の高空的飛躍は、低空に傾きしかば、再び内地向に立戻り、伊豫及尾濃の製品に類するものを製造するに至つたのである。
吉田の朝鮮向時代
之より先き明治二十二年、朝鮮京城の商估恒春號及び丁致國の兩人見本を携へ來り、石井種五郎の紹介にて、岡三平、大渡権藏、山口又七と特約して取引を開始した。尚之より先き同十九年に山口叉七、同二十年に石井檀五郎登窯を築造し。同二十六年には大串音松、又登窯を築きて着々と産額を擴大した。
吉田の大正景氣
其後恒春號等の取引杜絶するに及んで、山口又七は仁川に支店を設け、同二十九年大串音松は、伊萬里の陶商末石久次郎(1久)が朝鮮貿易を開始せるをし、之さ特約して大々的に製造販賣を開始した。同三十三年頃に至りては、各窯焼は直接又は店舗を設けて取引を擴大し、茲に朝鮮向製造の大正景気を現出するに至つたのである。
朝鮮輸出一手問屋定款
明治二十一年十二月十五日朝鮮國輸出一手問屋定款なるもの作成されしが、左に掲出して當時の状勢を伺ふ参考とする。
朝鮮國京城商業會議所ト結約シタル定書第二章第三條旨趣=基今般朝鮮國仁川港ニ於テ一ノ問屋ヲ設ヶ我肥前陶磁器販路ヲ擴張シ永遠ノ公盆ヲ目的トシ豫テ京城商業會議所卜氣息通同國需要者嗜好ニ適スルト否トニ注意シ粗製濫造ヲ以テ輸出前途塞絶スル等ノ害無カラシメンが爲メ此問屋定款ヲ設クル左ノ如シ
第一條
一肥前陶磁器輸出便宜ヲル爲メ朝鮮國仁川於一ノ問屋設ヶ朝鮮國輸出物品テ該問屋ニ於テ取扱物トス
第二條
一一手問屋大日本帝國肥前陶磁器一手問屋ト稲ス可シ
第三條
一一手問屋定期航海船舶ト特別輕減規約ヲ結運搬費額等該問屋取扱物品限リテ經費ノ多カラサラン事ヲ勉ム可シ
第四條
一朝鮮國輸出物品長崎港ョリ輸出分長港一手間屋ノ手數フ經伊萬里ョリ直航分伊萬里派出所手ヲス可シ
但本條箇所外ョリ輸送スルヲ許サス
第五條
一注文品アル時ハ同所問屋ハ見本及ヒ代價其他定規ノ要領書ヲ添へ其ノ注文フ要スル組合事務所へ通知ス可シ
但問屋ヨリ勝手に注文スルヲ許サス
第六條
一注文品受授際確定規約(朝鮮京城會議所ト取結ビタル規約第二章)ヲ履行ス可シ
第七條
一問屋貨物受濟上問屋ヨリ品名及と個數代價共記載各取締所へ届出可シ
第八條
一朝鮮國輸出荷物狀ラ各地委員ノ加印ヲ要シ第四條ノ手數ヲ經可シ
第九條
一同所問屋口錢藏敷並爲換金利子ヲ定事左ノ如シ
一問屋口錢賣込代百分ノ十下定ム
一運賃諸掛等費荷主負擔タル可シ
一歳一ヶ月壹俵付六厘トス
一荷物運賃其爲換金利子日步六屋トス
第十條
一荷渡節現損荷主ノ負擔タル可シ
第十一條
一荷物着港上直各荷主へ報知ス可シ
第十二條
一荷物着ノ上水火風災地震遭遇セシ時勿論荷主ノ負擔タル可シ
第十三條
一各地荷主於彼地へ直航スルモ大日本帝國肥前陶磁器一手問屋=據り之レヲ販賣ス可シ
但直航ノ者=シチ!手問屋ノ手ョ經スシラ賣却セ者物品代價差押內地各取所へ通知可シ
第十四條
一此ノ定履行期限滿五ヶ年下定メ滿期ニ至り尚之レヲ經績スル時ハ組合會議ノ上之レヲ決定ス可シ
但年限ト雖問屋=於不正所業アリタル時之ヲ更ス可シ
第十五條
一各地荷主ニ於テ競争濫賣シ又荷中不正品ヲスレ置キテ規則ヲ犯シタル者問屋於其物品代償ヲ差押へ其ノ顛末ヲ詳記シ直ニ各取締所へ通知スヘシ
第十六條
一第四條、第八條、第九條、第十三條、第十五條ヲ犯シタル者参圓以上五圓以下ノ違約金出サシム
第十七條
一前條ノ違約徵收金十分ノ七ヲ取所費充十分ノ三一手問屋附興スルトス
但各地違背者徵收金其ノ管轄取締所ノ經充ツ可シ
第十八條
一此定歇佐賀縣廳及長崎縣廳認可ヲ請と増減加除スル場合ニ於テ陶磁業組合取締所並大日本帝國肥前陶磁器朝鮮國仁川港一手問屋ト協議ノ上更兩縣廳認可ヲフ可シ
追加
一組合内製品組合外者=渡シタル時直=長崎一手問屋或朝鮮國一手問屋へ共旨通知シ買主拔ヶ出荷ノ節ニ對スル請求権限依頼爲スへキモノトス
一組合外者ニシテ聯合規約第八條ニ要スル承諾書ヲシタル上萬一揆ヶ出荷等ヲ爲セシ者再ど物品ノ賣却ヲ爲ス可カラズ
大音製
而して朝鮮向き好況時代に於ける吉田山製品の三分の一産額(約二十餘萬圓)は、大串音松に依って製造されしいはれてゐる。當時美濃や尾張の製品も、亦朝鮮向として彼地に輸出せられしが、それが皆大音製の銘を記入して販賣されし如きは、如何に吉田の製品が韓人に歓迎さしかを察するに除りある。
蚯蚓嵌止の研究
此間に擡頭せる製技上の研究としては、上繪附の完成であつた。元来何れの陶山も、凡て天草石を原料とする製品、殊に對州土の多量なる施釉物には、上繪附の際釉面に、必ず蚯蚓嵌なる赤線を露出するのが通有性であつた。
蓋し有田石の製品のみは、例ひ長く濕氣中に置かれても、敢て此礎質を現はす憂がない。
此研究は始め明治十三年精盛社にて試みしも、生地の關係に依って良結果を得ず、全く不可能事として推棄されたのである。同四十四年に至り笠原五郎甚だ之を遺憾とし、有田黒牟田の梶原墨之助を迎へて再び起業せしめ、傍ら副島茂八が生地製作の改良研究に依って、漸く之を完成するに至つた。今八寸大の組井や、蓋井、大外蓋及菓子碗等の日用向に、此上綸附(中附程度)が應用されてゐる。
吉田の石炭窯
大正十二年四月笠原平五郎、副島茂八、相川茂吉、石井清一、大串脇次等は、尾濃製陶地視察を終へてより、陶窯の研究となり、翌十三年より十五六戸の窯焼は、石炭窯に改築せしも、低價製産に於いては、一日の長ある尾濃品に敵し難く、加ふるに歐洲大戦後の経済界恐慌の一般不況に禍せられ、又再び内地向の製造に轉換したのである。
大正十五年の大旋風は、吉田山の陶業に大いなる損害を奥へしも、此地の當業者は不撓不屈之が復舊に努力したのである。此處の盛況時に於ける年産額は、實に六十數萬圓を算したりしも、現時は頗る低下されてゐることは申すまでもない。當今重なる窯焼には大串音松、石井清一、山口忠藏、大串脇次、大串兼次等十五六戸である。
大渡商店
又卸問屋として大渡商店ありて、窯元とも便利を計りつゝある(大渡權藏は明治四十五年卒去し、舎弟勇三郎大正四年卒し、末弟長八の男が現在の熊次にて、彼は今佐賀縣々會議員にして参事會員である)此地塩田町及鹿島町へ行程二里、嬉野町温泉へ一里を隔て、常に定期のタキシーがある。當今の不況と雖も、其製産額に於いては、外山中なほ第一の地位であらう。
大草野と空海
塩田の大草野は、平城天皇の大同二年(807年)僧空海(弘法大師)唐より歸朝するや大磐若經及十六善神を守護して此地に來り、真言宗正福寺を開基せしところである。其後嵯峨天皇の弘仁九年(819年)天下疫病流行しかば、空海に疫病轉除の敷あり、彼は都より再び大草野に来錫し、正福寺に於て磐若心経鍵を作り、大祈禱を結願せし傅へらる由緖地である。
韓人が此大草野に来て開窯せしことは、甚だ古きもの如く傳ふるも、前記の正福寺廢滅の趾が今畑地となり終れると同じく、其陶窯の趾を探ぐるも正確の地を指定し得ざるを恨みとす。
燈籠掛
只此處の山の神と稱する地に僅に小石を積める高麗といへるがあり、毎年八月頃に至れば、定日の設けはなきも、己がじゝ農閑の折を選みて、燈籠掛と稱するさゝやかな祭を催す位である。
此邊りより探收されし殘缺には、稀に無釉高臺の施釉茶碗などあるも、多くは全無釉陶にて、高火に焼締めしより地肌に光澤を生せしものらしく、そして茶碗の高臺の如きは、竹にてえぐりしものがあり、頗る元始的作品である。又此處にては、古く軟質青瓷を焼成せしさの口碑がある。今其製品を實見せざるも、此地方が宗教的にもそ需要せことは、必然の所縁さいふべきであらう。
眞言宗儀式と青瓷
當時弘法大師が、真言密教を流布するや、共宗儀の式に天部の諸天を供養するとき、必ず青瓷の佛器を用ひし由にて、それは支那傳來の法式であらう。加ふるに隣地鹿島は興教大師(康治二年十二月十二日(1142年)寂す、四十九才)の生地である。故に真言宗流布地たる大草野陶山に於いて、後年青瓷を焼きしとの説は、然る可き認識である。而して此地の斯業久しき以前に廢絶して、其沿革に就いては、全く調査すべき據がない。
敷浪
明治二十六年(1893年)小田志山の窯焼樋口覺左工門、此處の敷波へ来りて開窯し専ら染附の食碗を製造せしが、大正九年十月六十九才にて卒し、今嗣子彥三が斯業を継承しつゝある。三、四年前までは朝鮮向専門に製造せしも、今は食碗、土瓶 茶碗等の染附物を焼いてゐる。
原料は天草石に、三の股石の一乃至二割を加へて製作してゐる。先代開窯以来同業者とはなく全く樋口家一戸の陶業地である。此地方水利に便にして、諸に原石粉砕の水車場があり、他面此の水流豊なる大草野の名は、源氏螢の名所として耀いてゐる。
久間村は天正の頃、龍造寺氏の旗下久間權次郎盛種(薩摩守)の領地なりしが、其後鍋島氏の支配となりて、志田東山の外は、寛永十四年(1637年)より蓮池の所領となった。
冬野の土器
此地は既に王朝時代より植物を焼きしが如く、又近年冬野の池畔よりも土器を發掘せしが、それは少くも千年以前の作品といはれてゐる。
志田東山
久間の創始せられしは、明暦年間(1655-1658)韓人の子孫來りて陶器を作りし由傳説あるも、前記の如く藩祖直澄が、五丁田の陶業を此地に移轉せしてあるに因れば、なほ少し遡りて承應年間(1652-1655)の創始さ見ねばならぬ。
然るに此の古窯品なる物には、飴色釉や灰色釉の皿茶碗及び優秀なる三島手の大皿等を焼いてゐる、此事蹟に徹すれば、其以前に於いて韓人若くは其子孫等か、此處の陶器を製作し居たるにあらざるや想はしむるのである。而して共當時久間焼と稱せられは、後年の志田東山焼のこをさしたるものである。
志田西山
元祿年間(1688-1704)に於いて、志田東山より分窯されしものが志田西山である。故に東山にして西山を新山さも稱せられたのであつた。當時此處の古窯品にも、栗色釉に白の化粧掛を施せし腰下無釉の八寸の徳利や飴色釉の大茶碗など焼かれてゐるを見れば、矢張同時に磁器製作の外に、一部のくろ物が製造されしと見る可きであらう。
寛政年間(1789-1801)に至り、東西南山とも従来の吉田石に、天草石を加ふるに及んて、白磁の面目を一新するに至りしが、天保年間(1831-1845)に於いて、生産過剰の結果は、一時販路の閉塞を來せしより、雨山とも大いに衰頽するに至つたのである。
浦川與右エ門
此時西山の浦川與右工門(貞壽の父)は、奮闘努力斯業の回復を計り、藩主雲叟(直興)又資を貸興し、或は薪木を給するに及んで漸く復興する事を得たのである。
志田鉢
明治十年後は紙型捺染式染附にて、九寸、尺口、尺一寸、尺二寸の型打細工皿等盛んに製造された、之が所謂當時の志田鉢である。其他辨當及重箱等の製造も多額であつた。
浦川俊藏
西山製陶の發展に盡瘁せし者に浦川俊臓がある。彼は元蓮池藩士にて斯業を経営し大正十五年十月二十六日、七十四才を以て卒去した。(前大審院檢事浦川忠臓の父である)
松兵衛と軍六
西山の陶畫師にて、江口松兵衛といへる名工があつた。彼呉岳と號し、繪畫や彫刻の外、篆畫を善くし、永年有田の香蘭社に勤務せが、明治十六年三月七十一才にて卒去した。又久間村の仁平の男にて、浦川軍六(賴重)といへるは呉溪とし、弟錦水と共に陶畫の名人なりしが、呉溪は明治二十七年二月を以て卒去した。
藤津郡陶磁器會社
明治二十二年藤津郡陶磁器株式會社組織され、内野山の富永源六が社長であつた。同四十二年には、西山にて資本金三萬志田陶磁器株武會社が成立し、(今資本金拾五萬圓)杵島郡上野の野田卯入之が社長に就任した。そして大正の朝鮮向好況時代には、此處も亦多大の製産額をげたのである。
上久間山
上久間焼は、磁器製造を開始せしところなるも、當時は志田焼比較して、立値七合半立さいへる格落にて取引されたのである。今より十餘年前久間陶器株式會社創立され、平野重八其社長たりしが、今は解散されて彼は個人として営業しつゝある。其他現在の窯焼としては二三戸のみとなつてゐる。
志田東山は、元十數戸の窯焼ありしが、今廢滅して一戸の斯業者もなく、西山は前記の志田陶磁器株式會社の外二三戸の営業者がある。
西山の火鉢
現在の製品は重に瓶掛や火鉢類にて、原料は全く天草石のみ用ひてゐる。昔年久間三山の好況時代には年產額四十餘萬圓を擧げしさ稱するも、現時の産額は十二三萬圓であるさいはれてゐる。
上福の窯床焼
塩田町は、元龍造寺の旗下原豊後守尚家(十郎五郎)が、百五十町を知行せし舊地にて、鍋島領となりて後、寛永十四年蓮池の釆色にしたのである。享保(1716-1736)の頃韓人の子孫なる者、此地の上福に開窯し、佐賀鄉今山の原料を以て有田焼に傚ひて磁器を製作し、一名窯床焼と稱せられてゐた。今其製品を見るに、色相純白ならざるも、青素地に赤繪を施し、芝居めきし元祿人物を描ける細口の徳利があり、又同じ赤繪模様の油瓶などあるが、頗る古典味のある釉相を呈してゐる。
上福の製陶差止
然るに其頃佐嘉宗藩より、西次平(嘉次郎の祖)といへる者役義にて此地に赴任し、其際上福の磁器を見て珍敷思ひ、取敢へず宗藩に上申せしところ、抑赤繪附は有田皿山の秘密工業なるを、猥りに他所に於いて製造すること甚宜しからずとなし、こゝに上福焼が差留めらるゝに至つたのである。
鹽田の水利便
其後天草石の使用隆盛となり、該地方の原料は和船にて早崎海峡を越え、有明海より鹽田川を遡って此地に陸揚げし、塩田、吉田嬉野等諸川の沿岸なる五丁田、敷波、大草野等が何れも水利の便多きを以て、スタンプ式の水車粉碎を利用し、之に吉田石一割内外を加へ燒成火度を低減して製造するに至ったのである。
西 嘉次郎
斯くて塩田は、天草石運送船の要津として、各陶山への原料供給地たる媒介のみに止まりしが、今より五十餘年前蒲地定七(鶴太郎)此處に再び磁器を製造し、明治十八年西嘉次郎(彥作の父にて後年此地の製陶組合長)は、染附製重箱を齎らして、南洋新嘉坡より暹羅の磐谷方面まで販路の拡張を試みたのである。然るに該器の模様として書かれし昆虫が、彼等の宗教的見地より嫌忌されし爲め惜くも失敗に帰したのであつた。
盂買や浦鹽への活躍
明治二十年有田上幸平の丸田權九郎及惣平父子來つて又此地に製陶した。同二十二年に至り西嘉次郎は、佐賀縣陶磁器業組合副長(此當時の組合長は有田の平林伊平)として、再び印度盂買方面へ賣込視察の爲出張した。同二十五年に彼は又露領浦塩斯徳に渡航して、クルシカ(厚手の手附カップ)等を販賣し。同二十八年には、西比利亞方面へ出張する等、活躍大いに努めしが、大正九年五月十日七十一才を以て卒去した。
與三郎等の滿韓視察
明治三十九年九月廿三日此地の淵三郎(杉光和三郎の兄)は、東西松浦郡選出代議士川原茂輔及び有田の窯焼松尾徳助等と同時に、滿韓利源調査委員として、磁器販賣地狀況視察の爲出發したのである。
今塩田の代表窯焼としては、杉光貞雄、九田惣一(惣の舎弟)にて、其他に二三二戸がある。最初は志田鉢等重なる製品にて、其他は壺、重箱、辨など焼かれしが、今は火鉢、瓶掛の外食碗類を主として製造しつゝある。
第二窯業試験場
昭和二年冬佐賀縣會に於いて豫て懸案の窯業試験場設立案可決され、唐津の特志家高取家の寄附を得て、有田町の外此地へ塩田町に分設さる事となり、同五年十一月二十五日第二窯業試験場として落成式を舉行した。場長は第一窯業試験場長大須賀眞藏兼務せしが、同七年より元砥部工業學校長たりし重富英が専務場長として赴任した(英は同九年五月十日五十才にて卒したのである)
藤津郡陶磁器工業組合
昭和六年九月十一日に藤津郡陶磁器工業組合が創立され、同年十二月二十六日此地の杉光貞雄(和三郎の男)選擧されて、組合長となったのである。
美野山
五丁田村の美野も蓮池藩領にて、戸數百六十戶あり、此處は塩田町と近接し、武雄驛より三里の行程である。創始は當地の友八、徳十其他四五人の協同出資にて十間の登窯を築き、天草石に吉田鳴川石を加へて製陶せしも、幾許もなく廢絶し。其後堀江喜四郎復興せしも亦廢窯し。次に大川内の富永勝太郎來つて再興を計りしも是れまた廢窯に歸し、徒に陶煙の現滅を繰返す而己であつた。
大正七年五月有田の陶商青木幸平は、此地の大曲艶一、中島伊三をして電氣用器を焼かしむるこどゝなり、同十二年より艶一獨營にて前記青木の商品を製造しつゝある。なほ此外に大正九年よ染附食碗を主類として製造せる雄があり、そして此雨戸にて年産額一萬圓位といはれてゐる。
八本木山
八本木は舊鹿島藩領地にて、今の濱町の邊りなるを以て、一名濱山焼と稱せられてゐる。萬治年間(1658-1661)韓人の子孫來つて此地に開窯せしといはれ、其古窯品には土の上に白化粧を掛け、それに呉洲にて竹など描きし徳利があり。又同じ白化粧の上に菊の如き模様を文せる食碗等あるが、何れも全面に小氷裂を現はしてゐる。
岩永幸一
文久二年(1862年)岩永幸一が天草深江の原料を用ひて、磁器を製することゝなり、現今は石炭窯を築造して、楠田輿兵衛の一戸のみが製造しつゝある。製品の種類は、染附の燗德利及反茶漬碗等の下手物にて、製産額の如きは勿論少額であらう。此地古来より濱山燗瓶と稱する口附物が製作されたのである。
久保山
久保山も亦舊鹿島藩領地にて、此處は古枝村と稱し伏見及豊川と並んで日本三大稻荷の一なる祐徳神社の傍である。明治九年(1876年)鍋島彬智、久布白繁雄、山崎捷一、三原作右工門、鶴田惣吉、鶴田龜之助、村山廣吉、上野十太郎等協力して製陶を始めしものにて最初の窯焼は五戸なりしが、爾来哀頽し、明治十二年六月小野武則新窯を築造せしも振はず、今事業を繼續しつゝあるは鶴田惣吉一戸である。製品は八本木山同じく、天草石を主料として、爛瓶及茶漬碗の如き下手物を焼いてゐる。
上野甕
上野は杵島郡橘村にて、戸數二百戸を有し武雄驛より一里許りの行程である。此處は舊後藤氏の領地なるも藤津郡久間村と接し、戰國時代は雨莊の争奪地たりしに相違ない。上野焼の創業は、往昔久間村の韓人が、此地に来つて開窯せし由傳へらるゝも、今共事蹟としては全く不明である。
ハシカ杢之十
今より二百餘年前、ハシカ杢の十(本姓小田)なる者ありて、大形の甕を始めしより、其後此處は甕焼専門となり、其他は土管、水鉢、植木鉢等を焼いてゐる。甕の大なるは四石入があり、原料は此地小野原の粘土が使用されてゐる。製産額は今五千圓位と稱せられ、重なる窯元は、肥前土管製造會社(社長野田卯入)及山口秀吉の外四人にて、昔の窯ありし處は南上野なる今の會社の窯地である。
善平と清之進
明治三十四年大川内の名工柴田善平は、此處の山口秀吉方に來り、志田の粘土を探つて種々の雅品を製作しが、それは無釉から焼にて山水及び柘榴等を浮彫せし茶器や、手口附水指があり、水指には人物山水の片面に、二羽鶴が彫刻されてゐる、何れも拉車を用ひず、全くの手捻り細工である。そして善平は翌三十五年六月二日此工場に於いて卒去した。
次には山口縣人にて、清之進なる者又秀吉の工場に來り、此地小野原の粘土を以て、朱泥類似のから焼茶器を製作し、又鴛鴦形にて五寸の蓋物などの遺作がある。蓋し此處は甕類専門の製造地にて、此上野は以前甕野と稱せられたのであらう。
鳴瀬甕焼
鳴瀬甕焼も同し橘村にて、此處は高橋驛より、半里許りを隔てし九十餘戸の集落である。以前は此地方を芦原と稱せしが、後年檀家の關係にて、今芦原村落は橘村と橋下村とに二分されてゐる。明治六年(1873年)此地の田中民助、久保忠造、副島平吉等發起して十一間登を築窯し、武内村多々良の工人を招き、地元の粘土を以て甕類を焼きしものにて、中には大四石と稱す巨器をも製造された。需要地は筑後方面を重な得意先とし、又鹿児島の泡盛容器にも供給され年産額五千餘圜を繋げたりしが、明治二十四年に至つて廃窯した。
鳴瀬焼
鳴瀬燒は明治十三年(1880年)の好景氣に乗じ、前記の田中民助、久保忠造及副島龜三等の組合にて、六間登を築窯し、久間山の工人を雇用して、天草原料にて染附磁器を製造せしものである。種類は皿、鉢、食碗、火鉢等にて年産額三千圓位であつた。中にも久間山の名工浦川軍六か、描きし龍虎畫二尺鉢の如きは、抜群の物さいはれてゐる。又明治十八年東京上野五品共進會に出品して、副島龜三名義に賞牌を授かつたのである。斯くて明治二十三年に至つて廢窯した。
片白
片白も亦、同じ橘村にて五十餘戸を有し、鳴瀬と上野との中間村落である。明治三十年(4897年)前記鳴瀬焼の工人なりし、柿原久米吉此地に四間登を築窯し、天草原料を以て染附磁器の八寸刺身皿等を焼き、年額千五六百圓を擧げたりしが、五年許りにして廢窯し、後年陶器にて貯金壺、火消壺、擂鉢等を製作せし者ありしも、今や全く廢滅に歸してゐる。
直澄の産業策
此藤津編を終るに臨み、倩ら領主直澄が嬉野焼製産の主旨に就いて考察するに、従来多くの領主が、斯業を保護せし動機なるものは、何れも先づ自己の嗜好に出發して、道楽的に製作せしめ、而して後に始めて産業品として奬勵することが定であつた。
直澄に於いては然らず、別に藩窯さへも設置せすして、専ら日用品を主眼とし、只管領内の陶業を擴張すべく、南川原より指導者を招じて其意見を糺し、陶窯の構造を改めしが如き、洵に敬服に價する。而して此地元優良なる原料を産せず、良器の製作不可能なりし爲に、下手物のみを製せしと論する者あれど、然る時に於いて尚進んで之を試みんとすること、方に仕事の大名氣質を如實に示してゐるではないか。
況んや彼れ直澄は、當時の堅城として攻めあぐみし切支丹城へ一番乗りせし稀世の猛である。
彼の意志と共資力を以てせば、何を爲すさも不可能のことあるべきや。然るに想を領地民衆の福利に置き、斯業の興隆を主眼として厚く之を保護し、後代の領主亦大阪に於いて、嬉野焼として擴賣を爲せしが如き、専ら斯業の發展に留意せしものであつた。
釋大潮.
後代の藩主が陶業を督するに當り、像て彼が顧問として見逃かし難き一人物がある。それは蓮池龍津寺の住職釋大潮(名は元皓、字は月枝、松浦又魯寮子と號す、もと伊萬里浦郷家の男也、明和五年卒九十三才)にて、彼れ博學高徳、當時詩名天下に鳴りしは傑僧であつた。家康が天海を重用し如く、領主も亦深く大潮を信頼して常に其意見を聴きしことは周知の事柄である。故に嬉野焼産業の方針においても、高級品を要することあれば、高價を拂つて他山より購入し、自領の製品は大衆の日用品を目標として陶家を奨励し、且之が保護出資を豊ならしめし如き、又以て彼が大潮に私淑せし面影を見る可きであろう。
而して尚代の領主、及一面には吉田、久間諸山の陶家が又良く其意を奉戴し、一意日用品製作の工夫に没頭して、自己陶山の地位と大局を観察し、未熟なる骨董品などに傾想せざりしは感服の外ない。縦令優秀なる高級品のみを製造しても其需要を得るにあらざれば、下和が壁を抱くに等し、惟ふに名譽に倒れんよりも、恒産に生くることが産業の常道であらう。 嬉野焼の將來も勿論此方針なる可きも、一言蕪辤を述べて既往の経歴を讃する所以である。