

中興名物
高さ:7.1~7.4cm
口径:14.5~14.9cm
高台外径:5.3~5.5cm
同高さ:0.7cm
桃山から江戸初期にかけて、京都の唐物屋として知られた有来新兵衛が所持していたのでその名があります。新兵衛は京都の糸割符すなわち貿易商の一人で、遠州について茶の湯を学び、好みによる茶具を信楽、美濃瀬戸、備前などの陶窯で焼かせたとも伝えられ、当時一流の数寄者としで知られています。
総体やや薄作で轆轤(ろくろ)目細かく、碗形に成形され、口作りは端ぞり状をなしています。腰以下は全体に面取り状に削っていますが、高台ぎわの削りあとは比較的浅いです。しかし竹の節状の高台はかなり力感に満ちたもので、この茶碗の重要な見どころとなっています。また内部見込みはややくぼんでいますが、底から腰にかけての厚味はかなり厚いです。高台畳つきは胎土をみせ、その胎土はよごれのため、一見朽葉色のごとく見えますが、本来は灰白色のように見うけられます。内外全面に青味をおびた白釉がかかっていますが、そのなかに淡い灰褐色の大小のしみがほのかに散在して、味わい深い景をなしています。さらに高台ぎわにかけての釉調は、素地の削りあとの上にかかっているため、高台脇までちぢれのある独特の肌合いを見せて、高台そのものの作調とあいまって重厚な趣をかもしています。上胴にひっつきのあとらしい一文字の火間があり、また口縁の下に石はぜのようなひっつきもみられます。
総体的に素地、釉肌ともに、かなり堅く焼き締まり、まさしく堅手茶碗といえます。しかし長崎堅手のように、純然とした磁器質ではなく、またいわゆる雨漏茶碗ほど、やわらかいものでもありません。いわば雨漏状のしみが生じるくらいのやわらかさをもった堅手茶碗といえましょう。
内箱蓋表の「有来」の二字は、遠州の子、小堀政貴すなわち通称十左衛門の筆になり、蓋裏の「そはく茶碗の手」という貼り紙は、享保七年十一月に八十二歳で没した土浦藩主土屋相模守政直の筆といわれています。
また、その蔵品目録ともいえる『土屋蔵帳』には、「有来高麗井戸時代、ひびき有、袋茶地どんす。箱桐書付小堀十左衛門殿」とあり、さらに朱筆で、「伊賀様」の書き入れがあります。
『名物記』『古今名物類聚』にも所載されていますが、『名物記』の記述は、「有来茶碗 雨漏堅手古今之品 土屋左門所持、天明五巳八月十八日備覧(以下略)」とあり、寸法・箱・袋の次第がしるされ、蓋裏の「そはく茶碗の手」の貼り紙は、やはり土相州筆としています。したがって伝来は、土屋相模守政直所持、のちに松平伊賀守、さらに江戸十人衆の河村伝衛に伝わり、明治二十四年十月十七日に河村家の売り立てに際し、四百円で馬越家に入ったものです。
『大正名器鑑』では、土屋相模守の「そはく茶碗の手」という貼り紙を尊重してか、この茶碗を楚白手として扱っていますが、楚白は粉吹茶碗であり、白化粧がけを施していますが、有来は粉吹ではなく、化粧がけを施さない堅手茶碗であるところ、これは『名物記』の「雨漏堅手」とする見解に従うのが妥当と思われます。
(林屋晴三)

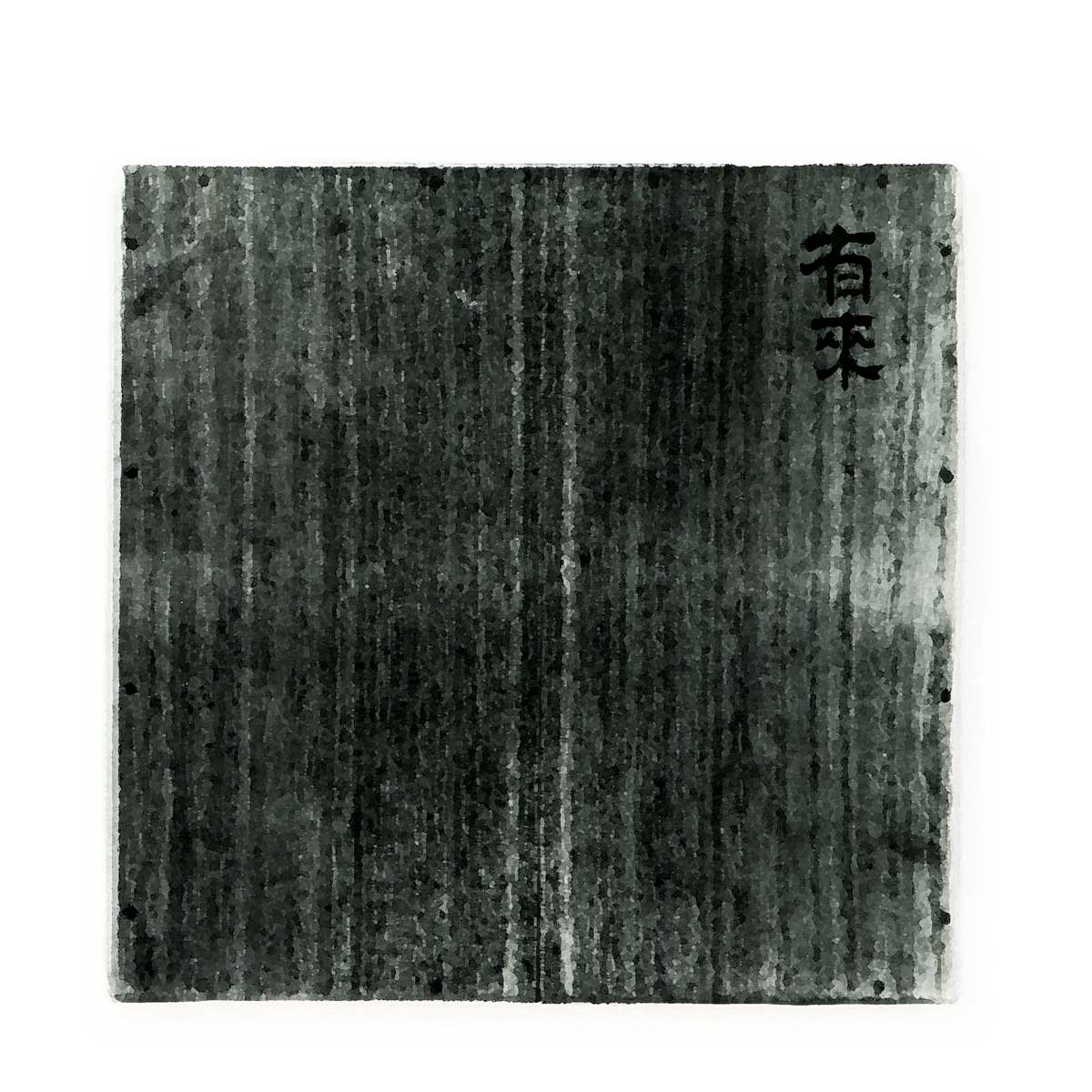

有来 うらい

堅手茶碗。中興名物。有来新兵衛が所持したことによりこの名があります。この茶碗を楚白とする説もありますが、端反り椀形で、竹の節高台をもち、釉が長石を主とした白色失透釉であることから、堅手と考えられます。形は均整のとれた井戸形で、土は硬く引き締まっています。総体に灰白色に青みが交わり、小さい斑文状の雨漏りじみが随所にみられ、景色をなしています。《付属物》内箱-桐白木、書付小堀十左衛門筆、蓋裏貼紙書付土屋相模守筆外箱-桐白木、書付松平伊賀守筆《伝来》有来新兵衛-土屋相模守-松平伊賀守-江戸十大衆河村伝左衛門-馬越化生《寸法》高さ7.0~7.2 口径14.ご不14.9 高台径5.4 同高さ0.9 重さ290
有来楚白 うらいそはく

中興名物。
朝鮮茶碗、楚白。
有来氏所持の楚白手茶碗で、前田侯伝来のものと共に楚白手唯二つの茶碗であります。
有来氏から土屋相模守、松平伊賀守、河村家、馬越家と転伝しました。
(『大正名器鑑』)


付属物
内箱 桐白木 書付 小堀十左衛門筆 同蓋裏 貼紙 書付 土屋相模守筆 外箱 桐白木 書付 松平伊賀守筆
伝来 有来新兵衛―土屋相模守―松平伊賀守―江戸十人衆河村伝左衛門―馬越化生
所載 古今名物類聚 土屋蔵帳 翁草
寸法
高さ7.0~7.2cm 口径:14.3~14.19cm 高台径:5.4cm 同高さ:0.9cm 重さ:290g
京都の商人、有来新兵衛が所持していたというのでこの名がありますが、堅手とも雨漏とも、類別すべき称はついていません。昔からこの茶碗についての記録はさまざまで、加賀前田家の粉引手、楚白の茶碗に類するかと思いますと、井戸茶碗や蕎麦と記している書もあり、正体不明に思案投げ首した様子がよくわかります。しかし端反り椀なりで、高台が広く竹の節であるくこと、釉が長石を主にした白色失透釉であることを見てゆけば、これが堅手・雨漏の線につらなるものであることは、ほぼ間違いないといえましょう。
ただこの茶碗の場合は、珍しく土と釉とがよくなじみ、貫入も出なければピソホールも少なくて、その結果雨漏りじみが殆ど現われなかったのでしょう。
そんなことで雪のように白い肌を保ったため、楚白の手とあやまられたに違いありません。今ならば、有来堅手とでも称すべきでしょう。





