

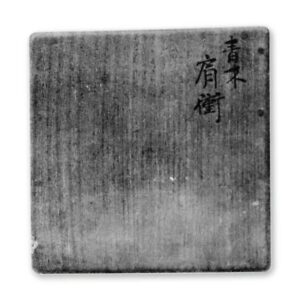

漢作 大名物 伯爵 酒井忠正氏藏
名稱
青木民部法印憲之を所持せしに依りて此名あり。
寸法
高 貳寸九分半
胴徑 貳寸四分七厘
口徑 壹寸四分
底徑 壹寸五分
甑高 参分參厘
肩幅 四分五厘
重量 参拾参匁貳分
附屬物
一 蓋 二枚 内一枚 窠
一御物袋 萌黄地純子緒つがり茶
一袋 二つ
下妻純子 裏上代海氣 緒つがり紫
紹鷗純子 裏玉虫 緒つがり茶
一袋內箱 桐 白木
肩衝 袋
一袋外箱 桐 白木
一挽家 黑塗
袋 白革 緒つがり茶
一內箱 桐 白木
青木肩衝
一外箱 桐 黑搔合塗 表裹共金粉字形
表 青木
裏 東照宮 御物 後腰庄三耶拜領 自後藤家贈來
一總箱 松 厚さ八分
雜記
青木肩衝 惟任日向守所持。 (東山御物內別帳)
青木肩付 御物惟任日向守上、右は後藤拜領の茶入。 (御物御道具記)
肩衝 唐物 大名物 後藤庄三郎、 (古今名物類襲)
天正八年十二月七日朝 惟任日向守殿會
人數 筒井順慶 津田宗及
床 二重かぶらの花入に水仙生て、床に大燈の墨跡(中略)、かたつき盆なしに、袋なしに、茶を入れて籠より取出し云々。 (津田宗及茶湯日記)
天正十年正月二十五日朝 惟任日向守殿御會
はかた宗叱 津田宗及
床にかたつき方盆、風爐平釜、上様より御拜領、始て手水間に、床に定家色紙、前に硯文臺、定家卿の所持也、手水の間にかたつき、水指の所へ引落て云々。 (津田宗及茶湯日記)
青木かたつき 御茶入(幕府のもの)朱書入 焼け候へども不苦。 (玩貨名物記)
森忠政 實は可成が六男美作守 慶長五年信濃更級以下十三萬七千石をたまひ、川中島の城に住す、八年美作守一園を賜り、十八萬五千石を領し、津山城を築く、大阪の役功あり、元和二年東照宮より愛染国俊の脇差を賜る、其後青木肩衝の茶壺をたまふ。寛永十一年七月七日京都にて歿す、年六十五。 (寛政重諸家諸)
青木 森美作守。 袋こい淺黄どんす。 二番御長持。 (御數寄屋御道具帳)
青木肩衝 森美作守上。 高二寸八分四厘、胴二寸五分二厘、板起し火氣あり。明暦三年正月十九日御炎上の節火に入り、御繕ひあり(茶入圖あり)。 (徳川公爵家道具帳)
(備考) 徳川公爵家道具帳に青木肩衝二あり。一は高二寸八分四厘、森美作守上れるものは高さ三寸、松平阿波守上れるもの是なり、又古名物記に「肩衝靑木法印より松平阿波守」とあり、青木法印とは民部法印淨憲の事にして、慶長十八年八十六歳にて歿せし人なり。
青木 唐物 大名物 後藤庄三郎、姫路公。 (伏見屋覚書)
青木肩衝 漢なり。伊木肩衝と同時代にして同手同藥立なり、又之を新田、勢高、不動等に比するに藥立同時代と雖も時代劣りたり。 (松平不昧公著瀬戸陶器濫觴)
青木肩衝 惣高さ三寸一分、口さし渡一寸四分五厘、胴さし渡二寸五分來、底一寸五分半、板おこし、袋二つ、下妻 裏海氣無地 緒つがり紫、紹鷗どんす 裏海氣無地 緒つがり茶 (茶入及底の圖あり)。 (幕庵文庫甲第十七號)
青木 高三寸五リン、横二寸四分半、口一寸五分、底一寸四分、こしき三分(茶入圖あり) (名物記)
傳來
元青木民部法印淨憲所持にして、一旦明智光秀に傳はり、其後徳川家康の手に入り、元和の頃森美作守忠政之を拝領せしが、忠政更に双之を幕府に獻せり、然るに明暦三年正月十九日江戸大火の節此茶入本丸の寶庫に在つて火災に逢ひ、箱類は悉く 焼失したれども、茶人は幸に大破せざりしかば、漆を以て之をひたるを、後籐庄三郎が拝領し、後藤より更に姫路酒井家に納まりしとなり。
實見記
大正九年十二月五日東京市小石川區原町酒井忠正伯邸に於て實見す。
口作少しく歪み、拈り返し淺く、甑下張り、其周園に沈筋一線繞る、肩キッカリと衝き、胴の上方にある沈筋は、茶入の約半分を絞り、底板起しにて其面に大小三ヶ所の火割れあり、總體青味を帯びたる地肌にて、肩廻りに焦茶色釉ウッスリと掛り、肩下に於て共釉光澤殊に麗しき慮あり胴體に漆繕いあり、裾以下鼠色土を見せ、底廻りに稍長き沈筋一線あり、内部口縁釉掛り、以下轆轤繞り、底の輪形中央少しく突出せり、總體青釉中に赤味を帯びたる飛び模様ありて、景色面白く、且つ口作の歪みたるなど、漢作として異風なるは、此茶入の特徴と謂ふべし。



