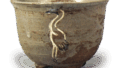宗室の阻諌
秀吉が出兵を企圖する其以前に於いて、彼の内命を受けし鳥井宗室(博多の豪商に徳工門重勝と稱す。元和元年卒七十七才)が普く韓土を視察せし結果は、此企圖が甚だ不利なるを認めて頻りに阻諌せしも、秀吉毫も之を容れす、刧つて彼が親近するを禁じたのである。
朝鮮出兵
時は文祿元年(1593年)三月十三日を以て、秀吉は三拾余万の大軍を召集し、此中二拾万五千五百七拾人を韓土に出兵せしめ、同三月二十六日自ら京師を發し四月二十五日肥前國上松浦なる名護屋城に着せしが、拾万二千四百拾五人の軍をして城外二里四方の周圍を厳重に警備ぜしめたのである。
第一軍の先鋒は、加藤清正(肥後國熊本城主)と小西行長(同國宇土の城主)を主將とし、清正は八千人(或は一万人との)を率ゐ、そして肥前國佐嘉の城主鍋島直茂之が副將として一万二千人を率る、又肥前上松浦鬼子嶽の城主波多親二千人を率ゐて直茂に属した。
小西行長は別隊となりて七千人を率ゐ、之に属せし肥前の諸將には、平戸の城主松浦鎮信三千人、島原の城主有馬晴信二千人、大村の城主大村喜前一千人、五島福江の城主五島純玄(淡路守始宇久大和守盛時) 七百人を率ゐ、清正と二道に岐れて進軍することゝなった。
鍋島軍の重なる部将
此時鍋島直茂に從へる重なる部將を擧ぐれば、山代孫七郎貞、田尻丹後守鑑種、成富兵庫助茂安、多久長門守安順、鍋島平五郎茂里、同三郎兵衛茂正、同新左工門種卷、同生珊入道道泉、同助右工門茂良、龍造寺七郎左工門家晴、同彥右工門家俊、同又八郎久茂、同太郎次郎茂成、同新介家光、同太郎五郎重統、同太郎九郎信成、同四郎兵衛信時、松浦太郎信昭、後藤十左工門家信、深堀中務太輔純賢小田四郎次郞信光、神代喜平次家良、姉川中務太輔信安、小川市左工門家俊、同半内家尚、千布宗右工門賢利、千葉右馬允胤信、犬塚三郎右工門茂虎、同興三右工門茂績、八戸助兵衛宗春、横岳下野守賴績、中山備前守信增、出雲兵部少輔信忠、大木兵部少輔純光、鹿江伯耆守信明、三浦四郎右工門賢純、木下四郎兵衛昌直、馬場太郎次郎信員、高木甚兵衛盛清、同與左工門胤清、同兵内泰幸、馬渡相右工門茂光、鴨打孫右工門胤純、同孫六家胤、中野神右工門清明、太田巳左工門茂連、内田助三郎家勝、土肥孫六郎茂實、納富又三郎家和、西牟田新介家親、平吉刑部丞茂慶、水町平右工門茂成、倉町半三郎家秀、嬉野休藏通直、同孫作通清等であつた。
解纜と歸國
斯くて直茂の軍は肥前國伊萬里港を解纜し、文祿元年(1593年)四月十二日両先鋒とも名護屋浦より出帆した。之より咸鏡、開城、安邊に轉戦し、直茂は清正と共に王城に入りしが、六月二十九日別れて吉州に向ひ十月永興郡に大戰した。同二年正月五日別軍の將小早川隆景(筑前名島城主)は、碧蹄館に於いて明の李如松が大軍を破りしも同七日行長平壌に大敗した。
文祿三年(1595年)明使來朝して和議成り。同五年十一月改まり慶長元年(1596年)正月に至り我軍悉く歸陣し、直茂又伊萬里へ皈港したのである。(此時直茂出兵記念として韓土の松を携へ帰り、此地木須の戸渡島神社「其後伊萬里相生橋畔に遷座し今又土井町へ轉座さる」へ移植せしものが、今の金比羅社下の松樹であるといはれてゐる)
再度の出兵
慶長元年(1596年)九月、和議破れて再び朝鮮の役を起し、同年十月二十日直茂は第一軍の軍奉行として伊萬里港より再戦の途につくや、長子伊太勝茂切に乞うて初陣し同二年七月十五日巨濟島の海戦に加はり、同年十二月陸戦に於いては明將楊鎬が大軍を夜襲して、清正が蔚山の重圍を解きし等苦戦交々なる折柄。同三年八月十八日秀吉伏見城に於いて卒去するに及び、同月二十五日徳川家康、前田利家協議して派遣軍を召還するに至り、直茂又諸將と共に筑前博多港へ歸陣せしは十二月上旬であつた。
戦後の考察
熟々此戰役の跡を考察するに、道路險悪且不案内なる異郷に於いて糧秣の微集困難なりし而己ならず韓軍中にも李舜臣や權慄等の如き謀略勇敢の將又乏しからざりしものとす可く。
加ふるに我先鋒の両主将不和にして行動一途に出てず、行長は途に平壌に敗走し餘軍又京城を捨て、南方に退却するの止むを得ざるの時一旦和議が講せられたのである。
次に再度の我が出兵軍は、多く全羅、慶尚、忠清の三道に楯籠りて遂に京城までは進み得なかつた。就中水軍の如きは甚しき敗北なりしが如く、今兵家の論するところに依れば、其際我が水軍の根據地が順西灣以西に及ばざりし爲といはれてゐる。
戦役の失敗
要するに秀吉の出兵は、明に打撃を加へ、朝鮮に大惨害を與へしのみにて、徒らに多大の人命と國帑を費し出兵軍の無双なる勇武を示したるの外實質的には何等得る所なき大失敗といばねばならぬ。せめて此出兵の一土産とも稱す可きは、彼地より多数の陶工を輸入して我邦陶技の進歩を促かし、然も當時不可能とされし白磁の製作を創業せしむるに至りしことにて、我が工藝史上且産業上特筆すべき事柄であつた。
出兵諸將の歸陣するや、秀吉より彼地の陶工を帯同せよとは命ざりしならんも、當時茶道の隆盛は名護屋城の本管に於いてさへ茶會を催し、或は其附近にて茶器を焼かしめしにしても、此際出兵の諸將中には韓土の陶工を需めたる者少からざりしことを察するに難くない。
朝鮮の建國
元來朝鮮の陶技は、地理的に支那より齎せしことは建国史上の経歴を有し、今より四千年前堯帝の時増君此地に來つて平壌に建國せし稱せられ、尋で三千六百年前殷の王族箕子逃れ來り、周の武王に封ぜられて樂浪(平壌を中心とせる王制地)に都を定めて四百年に及びして博へらる。
其後三韓に分封せしも、漢の元封三年武帝の爲に攻略されて四郡に分れしは、實に我開化天皇の五十年であつた。而して南部半島に建國せし任那は、崇神天皇の三十七年辰韓の地に建國せし新羅の爲に常に壓迫さるに至りしより、同朝の六十五年朝貢して我邦に援助を求めたのである。
樂浪の古陶
次に崇神天皇の十二年南部馬韓の地に建國せし百濟も亦、常に新羅の脅威に堪へす任那と共に我邦の保護の下にありしが、任那は欽明天皇の二十三年に百濟は天智天皇の二年に於いて何れも新羅の爲に滅亡するに至つたのである。而して是等韓民が、舊都樂浪時代より製陶の技に長しことは、今尚同地方より種々の雅陶が發掘さることにより明かに證することが出来る。
高麗焼の本場
斯くて醍醐天皇の延喜十八年(918年)高勾麗國(舊高勾麗は崇神天皇の六十一年建國)を再建せし王建は、朱雀天皇の承平五年(935年) 新羅を亡ぼして都を開城に定めたのである。此開城 (一に松都といふ京畿道)を中心として韓半島の各所に於て製作されしもの之れ則ち雅致なる高麗燒である。就中全羅道康津郡大口面、及七良面郡東西、又長興郡等其主なる産地にて凡を亀山天皇の元中九年に於て、李朝を建設せし李成桂の爲めに滅ぼさるゝに至るまで、盛んに製陶されたものである。
陶技の天才
之より國名を朝鮮とし、爾後李朝の製陶隆盛なりしも後年國勢の陵夷と共に衰退し、當時の一般工藝技術に就いては何等卓越なる藝術家なく、且其意匠の源泉たる可き名畫師とても有らざる中に、獨り陶技の工人のみ俊秀者の多かりしことを奇すべく、蓋し韓人は生れながらにして斯道の天才あるものか、それが一朝此戦役に際し悉く我邦へ浚はれたるの観を呈したのである。
韓人陶工の地位
抑朝鮮の陶工は、樂浪以來明器(副葬品及び玩具)の製造者として彼國の賤民級に属する者多く、之等の徒は士農工商と相伍し社会に列すること能はざる身分であつた。これ恰も我王朝時代の土師なる者が、後には凶禮陵墓一切の事を掌りし故に、社会より貶められしと相似たものであらう。
韓人陶工渡来の因
それが此際我邦に渡来すれば、各諸侯が自分の道楽と領地の産業の爲め競うて招聘し、中には世襲的の扶持さへ與へて優遇した。又韓人とても日本軍の路案内をなし或は糧秣の徵集其他敵軍への便宜を計りし者は、其儘國土に止まる能はばざる事情もあった。加ふるに此七ヶ年に渉る長き戦禍の爲め糊口に窮せる多くの韓人は、崇愛せる祖先の墳墓を棄て何れも家族を率ゐて渡せし者少からざりしものゝ如く、況んや日本に於てしかく優遇さるゝ消息が故山に傳はるに及んで、彼等の同族は鶏林八道に陶工の影なきまで渡せしとの説さへある。
薪材の缺乏
次には山林の濫伐であつた。彼等は百年の大計よりも、十年の小計さへ畫策せぬホンの目前主義に甘んする境地にあるの止むを得なかつた。もしそれ少しにても蓄へる者あれば地方の郡吏は種々の口實を設けて強制的に搾取するを以て、貯蓄心と積極的計畫心に乏しき彼等は只眼前の必要に駆られて山林を濫伐し、敢て殖林を成さゞるより年々歳々各地の峰巒は禿頭化し、遂には根株まで發掘して凌寒炊事の資に供するに及び、殊に大量を要する製陶の燃料に於いて全く窮乏を告げし事も亦大いなる一因として敷ふ可きであらう。
重量代り
他の半面に於ける理由としては、此戦役の際頻繁に往復する我運送船の釜山等より歸航する時に、當時の小船にては空荷の儘玄洋の波濤を乗越すことは甚困難なるを以て、その度毎に之が積荷代りして彼等を乗船せしめし如く、又其頃より釜山海邊の寺院や墓地に於ける古塔、釣鐘及燈籠或は目ぼしき石像の如きは皆搭載されて殆んど跡を断ちしてまで稱せらる。斯くて多くの韓人は何業者をとはす此機會を以て、唐津伊萬里平戸の諸港へ續々と上陸せしに相違ない。
直茂と韓人陶工
而して地理的關係の至便なる上に一番多くの軍勢を率ゐし鍋島直茂が又多数の韓人を連歸りしとの説あるは、歸航船の頻繁なりし丈け其然るを肯定す可きも、其數幾千人なりしや將幾百人なりしやは詳でない。蓋し直茂個人しては細川忠興や蒲生氏郷又は田中吉政等の如く點茶的風流者でなく、彼が多くの生涯は龍造寺隆信の爲め九州征服の戰務に没頭し晩年には肥前領内の統整に従事して治國に寧日なき観があつた。
故に彼が茶事風流の為に、此際多くの韓人を連らざりしは勿論として、又最初より自領の陶業企圖して彼等を帯同せしとの説は首肯するに躊躇する。彼の李参平を渡來せしめし動機の如きも全く人情として止むを得ざりしより起りし事は後段に於て詳記すべきも、李が偶然に有田泉山の磁礦を発見して始て白磁を完成せしより、髪に國産として獎勵保護の道を執りしものと見る可きであらう。
本編は往時より、肥前の佐賀、唐津、武雄、藤津、伊萬里、平戸、大村、諫早等に渡來せし各種の韓人系を主題として、分類的に記述すべきも、此際肥前以外の諸侯が、朝鮮役後自領に於いて開窯せしめし斯系の概略を記述する。
高取焼
黒田長政に從ひりし朝鮮慶尚南道韋登の人八山と、同時に加藤清正に從ひ來りし八山の舅新九郎は、共に長政の命に依り領内に製土を探見して、筑前國鞍手郡高取村に開窯し之を高取焼した。そして八山は井土八臓と改めて七十人扶持を給與されたのである。
寛永五年(1628年)黒田忠之(長政の長子右工門佐)は、唐津寺澤氏の浪士五十嵐次左工門を召抱へ(三十人扶持を給す)、八藏と協力して斯業を改良せしめた。小堀政一又此地に来り次左工門及八藏其子八郎右工門とに託して、光澤ある褐色、淺碧或は白や黒釉等種々の名器を製作した。之より高取焼遠州好み七窯の一に敷へらるゝに至つた。
慶長十九年(1604年)高取焼は、同郡磯村へ移り寛永七年(1630年)又穂波郡合屋村白旗山の麓に移り、次に寛文七年(1667年)上座郡鼓村へ轉じ、又同郡鹿原村へ轉じ、寳永年間(1704-1711年)再び鼓村へ歸りしとき福岡城の南方田島村の東松山へ分窯し、享保元年(1716年)同市西新町の東山へ移りて藩窯となったのである。
小代焼
加藤清正韓土の陶工若干名を連帰りし中に、肥後國玉名郡小代山の麓に於いて、小代焼(又龍ヶ原焼)と称する垂下釉の砂器(炻器)を創始した。寛永九年(1632年)細川忠利(忠興の長子越中守)豊前より此地に封せらるるや、牝小路又左工門葛城安左エ門來りて製陶せしを忠利大いに保護奨励した。後年野田又七の先人窯を南關町の堀池園に移し一に松風焼と称するに至つた。
島津義弘韓土の陶工芳珍(金海)朴平意(又朴興用)朴正記、沈當吉、及伸、李、姜、陣、鄭、車、林、白、朱、崔、膚、金、阿、丁等の拾七姓二十二人(或は四十四人とも)を引連れて歸國、そして芳珍を鹿児島(今の高麗町)に居らしめ、朴平意を日置郡串木野鄉下名に居らしめた。
帖佐焼
後義弘姶良郡帖佐城へ移るに及び、芳珍をして開窯せしめしもの帖佐焼である。芳仲は歸化名を星山仲次と改め祿十五名を給せられた。作るところの陶質緻密にて鼈甲、虎斑、及白色凝釉の斑々たる蛇蝎の如き世に古帖佐と稱せらるゝものである。此中最適意のものにて義弘自ら捺印せしものを御判手と呼ばれてゐる。
慶長十二年(1607年)義弘同郡加治木城へ再轉するや、仲次又此地に来り加治木郷龍の口に開窯した。仲次の男喜兵衛、藤兵衛共に河原を姓とせしが、喜兵衛の男小右工門に至りて山元と改姓するに至り、寛文四年河原、山元二家共に同郡龍門司に移窯したのである。
苗代川焼
是より先慶長八年(1603年)義弘及子忠恒(大隅守)は、朴平意、朴正記、沈當吉(沈壽官の祖)等をして薩摩國日置郡伊集院鄉なる苗代川村に移さしめしが、平意勤苦力を尽し同十九年に至りて白砂及白粘土等を発見して苗代川焼を完成した。其白磁に類する純白なる白薩摩を始め玉子手、刷毛目、三島手、寸古祿等を製作するや義弘又其優なる物に捺印して之を勤奨し以て御判手を遺すに至つた。弘化元年(1845年)朴正官は此處にて金欄手に成功し、安政四年(1858年)沈當壽の十一世沈壽官藩設の工場を督して盛にせものである。
竪野焼
元和五年(1619年)島津家久(義弘の長子薩摩守)居を鹿児島に移すに及び、仲次の男星山彌右工門金和、舍弟休左工門金林之に從ひ、城下の下竪野に移窯せしもの即ち竪野焼である。一説に前記河原藤兵衛の第二子十左工門小山田村に分窯す、其子十左工門芳工叉製陶に巧みなりしが、明和五年(1768年)出でて竪野の藩窯に來り、寛政五年(1793年)藩主に乞うて肥筑の陶窯を、次に長門備前の諸山を経て京の焼を研究し、歸國して鮫焼の如き良器を製作せしといはれてゐる。
上野焼
慶長三年(1598年)加藤清正に附きりし朝鮮泗川郡十時郷の人尊階なる者、一時唐津に止まりしが、慶長五年(1600年)細川忠興に召されて豊前國田川郡上野村に於て上野焼を創始し、上野喜藏高國(名は甫快字は如公)と改名して、五人扶持十五石及雜石二石を給せられた。
忠利熊本へ移封せらるゝや、高國の子十時孫左工門甫久及四男渡久左工門高利止まりて小笠原忠政に仕へ、そして上野燒を継承した。其製造は藩費を以てし製品は悉く藩庫に納めしが、寶暦七年(1757年)甫好に至り專賣を請うて許され、文化元年(1804年)甫紹藩命にて京工京兵衛に就きて樂焼の法を習得し、功につて騎馬従者を許されたのである。
高田焼
忠利に從ひて肥後に移りし高國及長子上野忠兵衛(寶盞と號す) 三男藤四郎は、八代郡高田鄉奈良木村に開窯して高田焼創製せしが、萬治元年(1658年)下豊原村へ移窯した。高田燒一に八代燒さ稱し、赤褐にして紫色を帯び又は、黄黒の垂下釉を施せがあり、或は坏質薄うして灰青色を施釉せる茶器がある。四代藤四郎に至つて黒白嵌土の法を案出し、釉法も紫驂色に改めたのである。
古萩焼
甞て對馬に在りしを唐津の寺澤廣高に召されし韓土の陶工李敬は、歸化して坂本助八道忠と改めしが、慶長三年(1598年)毛利輝元に聘せられて長門國阿武郡椿郷東分村松本に来り、古萩焼を創始して韋登及割高臺等を製作した。其器質密ならず釉色は多く白黄淡薄である。そして彼は五十余石の高祿を給せられたのである。
寛永二年(1625年)十月秀就(輝元の長子長門守)は、助八へ高麗左工門の名を興へしより爾來坂高麗左工門と稱するに至り、同二十年二月十一日七十五才を以て卒去した。(寛文年間同地萩の松本に於大和國三輪村の人休雪來り、質密にして釉溜りあるものを製作せしを、別に松本焼と稱するに至つた)
以上列記せるは其重なるものにて、此九州諸藩に於ける開窯が、我邦の製陶界に大いなる啓發をせことは申すまでもない。而して此製陶の結果も亦従来の製陶史と同じく、陶器より炻器に止まりて未だ白磁を製するに到らなかつた。たゞ苗代川の朴平意が手に依って、白磁類似の白薩摩を製作せしも、それは質に於て堅緻ならざる陶器であつた。
我國製陶の経路
元來本邦の製陶史は、土器より陶器に移る間は頗る牛歩的の觀ありしも、一度び瓷器及炻器を製作するに及んでは、一般の文化共に長足的の進歩を示したのである。然るに永年此間に安んじて何等胎質上の改良を試みざりし所以があらねばならぬ。而して又共頃には已に支那渡の磁器に接しながら、なほ此方面に研究の手を進めざりしは何故であらう。
志野風施釉
勿論當時に於いて、天然の磁石を得ずして此種の製作は容易ならずにするも、瀬戸又は唐津の諸窯にて彼の志野風なる乳白手の施釉物を製しながら、一歩を進めて胎質の工夫に及ばざ所以を考察するに、是我邦人が茶趣味上雅陶を愛して、磁器への進展を深く促さぐりし結果見るの外ない。
邦人の雅陶趣味
我邦人の雅陶翫賞は實に徹底的にて、青瓷に謂支那の紫口鐵足等の如く、窯變釉色の調和には脂質の色相にまで吟味からす故に志野の白釉も陶質の胎土に施され、且其釉際に胎色味を呈してこそ愛好されしものであらう。
其他多くの陶器は褐色或は鉛色の上に化粧(九州では天草石などを用ひ、備前では三つ石の蠟石を用ひ、瀬戸にては蛙目を用ふ、エンゴーベとは英獨佛語の由である)を施し、或は諸種の刷毛目を文し、又は施釉の上に粗笨なる模様を現はして深玄なる雅致を需めたのである。
若し我邦の製陶研鑽が、瓷器當時の趨勢を持續したらんには、唐宋以来彼と雁行せし日本の陶技は、或は支那より先に磁器の製作を試み得しやも計られなかった。況んや歐洲の陶技の如きは、凡ての文化と共に遙か我邦の後へにありしことは申すまでもない。
陶器と磁器
而して日本人にのみ理解さるゝ茶趣味の翫賞からは、窯變の妙、胎土の味、箆の作行、手捻りの技法等、土器や陶器にのみ持てる特殊の妙味は到底磁器に見出す能はすとするも、我邦人の潔癖性より考ふるも洗滌に便利にして、且衛生的なる白磁の必要なることは當然であらう。
畏こくも大内の御食器が、有田磁器の創製後幾許もなく此地の辻喜右工門へ調進の敕を下された。
況んや日用品として堅緻の点に於いても陶器より數等の上にある磁器である。
近年流行せる硬質陶器の如きも、若し燒成の不完全なるに於いては、素地の吸水性の爲に生する熱膨張の結果は釉面に嵌入を生じ、汚物や微菌の浸入する恐なしさせぬ。又寒暑に對する素地と釉薬が収縮の差より釉皮が剥脱して、美親は勿論食器としての資格が全く失はるゝことがある。
進歩的製陶
磁器に至つては、胎土釉薬共に高火度を以て燒貫かれてあるからに何等の變質もない。又之を科學的に考ふるも、従來鐵分多き胎土や釉薬を以て暗色の陶器を而已焼きし時代より、鐡分少なき胎土と釉薬を擇みて透明の白磁を製作せことは、大なる進歩たることを疑はぬ。而して此製作が我邦の神代より結縁淺からず(新羅の建國は神武天皇の皇兄稻氷命と稱せらるゝが如き)そして今や同國の件に入りし韓人に依つて創製さしことも一因縁といはねばならぬ。
大川内子爵の陶系大別
我邦の陶系と作風は、大川内子爵の大別せし如く四つの系統に分つべく一は古雅式の瀬戸風にて、一は純日本式の京都風であり、一は朝鮮式の唐津風にて一は支那式の有田風である。勿論有田は唐津と同じく朝鮮をさすべきも、支那の青花や赤繪に倣うて早くも支那式に轉換せしものである。