

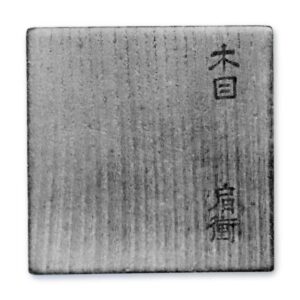
漢作 大名物 侯爵 前田利爲氏藏
名稱
命名の由来審かならず、然れども南葵文庫本朝倉越州記に「信長殿江州堀竝に阿閉と云ふものを九月中旬に木目の山城に城守に置き玉ひける」とあり、左すれば木目城は朝倉領にして此茶入は城と共に信長の手に入りたるが故に此名あるに非ずや、姑く記して後の識者を待つ。
寸法
高 貳寸九分
胴徑 貳寸五分五厘
口徑 壹寸四分
底徑 壹寸五分
瓶高 参分五厘
肩幅 四分五厘
重量 参拾六匁四分
附屬物
壱蓋 一枚 窠
一御物袋 茶羽二重 緒つがり茶
一袋 二つ
本能寺切 裏茶海氣 緒つがり天鷲織
廣東織留 裏茶海氣 緒つがり茶
(備考)名物記、古今名物類聚に、袋三つとあり、其中彌左衛門廣東の古袋は破損せり。
一袋箱 二つ
木目かたつき袋
とんすほんのうち内
木目かたつき袋
かんとう鳥にこんノ打とめ
一木形 桐製 一筒
廣東織留の袋に入る
一挽家 鐵刀木 内かりかの紋純子
袋 萠黄地純子木瓜内梅鉢唐花小紋 裏鶉海氣底朽チ 緒つがり焦茶
一內箱 桐 白木 書付遠州 裏書付張紙
表
木目 肩街
裏
漢木目肩衝(朱書)台德院様より徼妙院様御拜領其他由来有之
一外箱 桐 春慶塗
一總箱 桐 白木
木目肩衝
雑記
きのめ 福島左衛門大夫殿。 (東山御物内別帳)
木の目 松本淡路殿。 (玩貨名物記、古名物記、鱗凰龜龍)
(備考)松平淡路守は加賀侯松平利常の二男利次なるべし。
木乃目 唐物 大名物 松平淡路守、高二寸九分、胴二寸六分二厘、肩二寸二分四厘、口一寸四分八厘、底一寸五分二厘 こしき四分、蓋一枚、袋三、八左衛門漢東 裏もえぎ海氣 緒つがり遠州茶、純子本能寺切 裏もえぎ海氣 緒つがり天鷲織、漢東 裏もえぎ海氣 緒つがり紫。挽家たがやさん内張かりがねの紋純子袋萠黄地木瓜の内櫻角唐花色の紋 裏鳥海氣 緒つがりコゲ茶、箱桐白木、蓋裏書付如此。 「漢木目肩衝台徳院様より微妙院機御領其他由來有之」如此張紙にて書付有之。 (古今名物類聚)
木目肩衝 唐物 松平伊賀守(加賀守か)所持、元文五申十二月十日借覽(寸法附属物、茶入圖あり)。 (名物記)
福島正利 正則之子 寬永九年台徳院様に父が遺物正宗の刀、青江國の脇差、きのめの肩衝を獻す。 (寛政重修諸家譜)
福島正則遺物覺 木目かたつき、正宗の御物、青江國次の脇差、右公方様、寛永元年七月五日正則制。 (高木文二郎氏藏福島正則文書)
前田利常 小松中納言 元和九年台徳院の遺物後藤正宗の御刀を奉る。之より先き利常参勤の折から、郷の御刀、富田の御刀、鳥飼岡の御脇差、貞宗朱印の御脇差、戸川國次、來國次の御脇差、木目肩衝の茶入、定家筆八重棒の色紙をたまふ。 (寛政重修諸家譜)
木目肩衝 漢、土紫、下藥柿、上薬黒、盆付板起、置形右の後方に石はぜの痕あり、其間に連麟せるふくれ大小四ヶ、茶入内方置形に對し、外上藥長短二筋垂るゝ。 (前田侯爵家道具帳)
傳來
元福島正則所持、寛永九年其子正利父の遺物として之を将軍秀忠に獻じ、秀忠更に之を前田利常に賜ひ、其後利常次男の家に俺はりしが、再び本家の所藏に帰して今日に及べり。大正四年七月十日東京上野公園美術協會內竹隣庵開席の際、宗半肩衝と共に、前田侯爵家より出陳せらる。
實見記
大正八年十一月二十五日東京市本郷區本富士町前田利爲侯邸に於て實見す。
口作粘り返し深く、甑際に一線を撓らし、總體黒飴色釉に薄紫釉斑を成し、光澤鮮麗物を鑑すべし、置形一段濃厚なる黒飴釉、肩先より流れ掛りたるが胴に至りて綜合して一ナダレと成り、裾の邊に至りて止まる。裾以下朱泥色土を見せ、木目の如き小孔二ヶ所あり、板起しにて底廻りギザギザと缺けて不規則なるが頗る雅致あり手磨れなく新に窯を出でたるが如く綺麗なるは漢作茶入中稀に見る所なり。内部口縁釉掛り、以下淺き轆轤続り、底中央の鏡落ち輪状を成すは、最も珍しく見受けらる。




