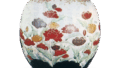抹茶碗の正面見込みにかすかに巴形の凹所があるようで、茶溜まりといって茶碗の見所の一つとされます。
楽茶碗にはおおむねことさらに茶溜まりをつくっています。
巴形にしたり、一端を深く一端を浅くなだらかにするなどの工夫があります。
茶溜まりはおそらく、最初は朝鮮茶碗に自然にあったものを、景色として茶人の間に愛好され、のちには一つの約束のようになって佗びの茶碗には必ずこれをつくるようになったものであるでしょう。
瀬戸系の茶碗では瀬戸黒に初めてこれがみられます。
中国・朝鮮などに多く見られる「鏡 かがみ」と同様に、器を成形する際に底が割れるのを防ぐため見込みの中を強く押さえて締めて作った跡のようです。
カオリン質が少ない土ほどよく締めて作らないと高台が切れたりします。それを防ぐため篦などで締めて仕上げます。その名残をのちの人が茶たまりと称したのでしょう。